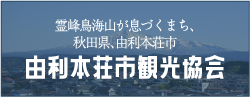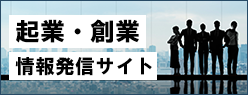石碑12「満州開拓の碑」

石碑12「満州開拓の碑」の説明
昔、日本国は、現在の中国領土の中に「満州国」を建設し500万人の日本人を移民して食料等の増産を計画しました。昭和16年(1941年)に現在の由利本荘市を中心に「満州国第十次由利郷開拓団」が結成され、昭和19年(1944年)には佐々木三郎団長以下、総員350名は素晴らしい成果をあげ、秋田県は県の開拓団40段の中でも最大規模の開拓団として評価されました。しかし、終戦と同時に匪賊の襲撃や餓死、病死等、多くの命が失われ日本国にたどり着いた人はわずか129名でした。
国家のために荒野を開墾し増産に励んだ団員の努力と多くの犠牲者への鎮魂を「満州開拓の碑」に込めて、後世に伝えたいと願い、生存者によって建立されました。
- 作者
-
佐々木けいし
松ヶ崎神ノ沢出身 佐々木三郎団長の孫
東京藝術大学大学院修了、北海道教育大学教授
本荘東中学校校章制作、本荘南中学校正門前モニュメント制作
- 意図
- 大地を開拓する人物と動物(牛、馬)をイメージし、鎮魂の意図を込めた、緊張感あふれるコンテンポラリーアート(現代造形)
- 表現技法
- 真鍮、ステンレス等を素材にした「鍛金」の技法で制作
- 建立
- 平成元年8月19日
満州国第十次由利郷開拓団60回忌慰霊祭
平成17年は、戦後60年の節目を迎え、私たちの満州由利郷開拓団が消滅した悲しみの深い年に当たります。夢を抱き渡満した総員350名も、今は数名になってしまいました。元気をふりしぼって、皆さんが永眠する由利本荘市、鶴舞(本荘)公園「満州開拓の碑」の前で、慰霊祭を行います。
振り返って、昭和16年(1941年)は、我が国の紀元2600年の記念すべき年に当たっており、国策の一貫として、由利郡農会は31ヵ町村の記念事業として私たちの「満州由利郷開拓団」を胎動させました。秋田県は、開拓団を10段階に分けて派遣し、我が開拓団は10次派遣の最後の開拓団になりました。満州国(現在は、中華人民共和国)に食料増産、第2の故郷を築こうとしたのです。本荘部落、西滝沢部落、鳥海部落、八塩部落など、郷土の名をそのまま命名し、遠い故郷に想いを巡らせていました。所在地は、満州国牡丹江省嚀安県(ムータンチンアン)営城子であったので、正式名は「満州国第十次営城由利郷開拓団」と呼ばれています。現在の東京城(とんきんじょう・我が国と最も古い交渉のあった渤海王国の首都)駅から、西方向30キロ地点に本部が設置されました。(北緯44度00分、東経129度20分の地点)
先遣隊25名の現地入りから出発した開拓の職務は、あらゆる苦難を乗り越え、みるみる秋田の第二の故郷をつくりあげていきました。昭和19年(1944年)には出生数45名を加え、秋田県派遣の44団の開拓団では最大規模の350名の総員に達しています。中でも力を入れた赤レンガ作りの国民学校の建設は、全国の開拓団でも稀なる堂々たる建築としてうらやまれました。我が団の耕作・水田を含む総面積は、約18,000町歩と広大なもので、これに伴う輸送用大型トラックや農耕用トラクター等も完備し、牛馬も288頭も保有していました。3年間の試行錯誤の結果、昭和19年から昭和20年(1945年)にかけて、稀なる豊作が団員を潤し、主食充実、味噌、醤油、初めて成功したチャンチュウ(酒)工場など、新しい農業文化生活の理想楽土を誰もが実感しました。
しかし、終戦が近づくにつれ、男性のほとんどが徴兵に動員され、昭和20年8月、突如としてソ連参戦による満州国境に異変が起こり、昭和20年8月13日午前10時、満州国警察から「直ちに避難せよ」という命令が下った。それまで築き上げた我が家に火を放ち、逃げるがごとく境泊湖を目指して悲劇の避難行きが始まりました。その後、再度の命令がくだり「敦化(トウンホワ)をめざせ」とのことで、情報の不正確さに迷いながら、祖国の方向をめざして日夜ガムシャラに歩みを続け、幼子の泣き声だけが今も耳に残っています。また、ソ連軍の略奪が激しく、本道を避けて山中をさまよい、草の根を食しながら命をつないだのも心に残っています。
昭和20年9月6日、共に避難を続けていた他の開拓団や日本軍の現地除隊兵も加わり、3,500名の難民集団となって行動していました。敦化から額穆策(がくぼくさく)、蚊河(チャオホウ)を通過して、山沿いに吉林(チーリン)、新京(現在の長春チャンチュン)を目指すことになっていたようです。由利郷開拓団はこの難民集団の総合指揮をとることになり、佐々木団長、進藤副団長、進藤校長等は、現地民との交渉、食料確保、生命維持のすべての運命を任せられていました。
昭和20年9月11日は、避難行き41日間の最悪の朝を迎えることになりました。私は長蛇の列の先頭にいましたが、午前8時に出発の合図があって間もなく、後方の丘から機関銃が撃ち込まれ、400〜500人の匪族の襲撃に遭いました。弾丸は耳元をピューンピューンと唸りをたててかすめ、死体や泥に埋まった人間の上を飛び越えて、どこまでも逃げました。1時間くらいの襲撃が続いたでしょうか、銃声が止み、ふと気がつくと匪族は私を追い越して遥か前方で銃を構え、降伏したひとりひとりから一切の金品などを掠奪している光景が見えました。進藤学校長は日本製銃剣で額を刺され殉職。副団長は頭部の裂傷にて重体となりました。
昭和20年9月29日、新京にようやくたどり着き、長春市大屯区南大房身地区陸軍官舎跡の開拓難民収容所に入ることになったのです。この収容所では、各地から続々集まった開拓団、元日本軍人等、約8,000人がどん底生活を強いられました。この収容所の会長に我が開拓団団長、佐々木三郎(私の父)が選任され、毎日ソ連軍の所へ、私を連れて「食料交渉」に出かけた記憶が鮮明に残っています。
南大房身の生活は言葉では表し得ないほど、残酷で悲惨な冬越しとなりました。マイナス25度の厳寒に暖をとることもできず、発疹チフスが蔓延し、毎日のように飢えと衰弱で仲間が死んでいきました。死体は埋めることもできず、家の後ろで、カラスや野犬に食いちぎられていくのを見過ごすしか方法はなかったのです。
昭和20年11月に父が病死し、私は新京の町で、乞食をやったり、閉鎖された廃坑にもぐって、石炭やコークスを拾ってパンと交換するのが日課となり、食えるものは何でも捉えました。由利郷開拓団の避難行き総人数は233名、このうち、41日間の避難移動中に死亡した方11名、南大房身での僅か10カ月の間に亡くなった人数は104名で、なんと48パーセントの尊い人命が南大房身で失われた最悪の場所であったと悔やんでいます。
昭和21年(1946年)7月8日、我が団が貢献したことが認められ、長春第一回移送として選抜され、生き抜いた117名(現地復員者3名含む)が引き揚げの先陣となり、昭和21年7月15日、胡芦島から乗船し、昭和21年7月21日、夢にまでみた日本の国、広島県大竹港に上陸し、手を取り合って喜びを分かちあいました。
帰国後の慰霊祭等の主な活動は、次のようになっています。
|
慰霊祭等の主な活動 |
|
|---|---|
| 昭和21年(1946年)8月10日 | 本荘町東林寺にて合同慰霊祭 |
|
昭和22年(1947年)3月27日 |
「開拓民自興会」由利支部を結成(支部長:佐々木健三) |
|
昭和22年(1947年)8月20日 |
秋田県開拓物故者合同慰霊祭に我が団から50名参加(秋田市寺町「妙覚寺」) |
|
昭和26年(1951年)8月24日 |
本荘町東林寺にて七回忌大法要会 |
|
昭和27年(1952年)6月2日 |
「満州由利郷開拓誌」副団長の進藤孝三著発行 |
|
昭和52年(1977年)7月16日 |
本荘町東林寺にて33回忌並全物故者合同慰霊祭 |
|
平成元年(1989年)8月19日 |
本荘公園に「満州開拓の碑」を建立 除幕式を挙行(県内唯一の鍛金によるステンレス真鍮銅の金属による慰霊の彫刻を本荘市に寄贈) |
|
平成2年(1990年)1月31日 |
「満州由利郷開拓誌」副団長の進藤孝三著再版 |
|
平成6年(1994年)8月21日 |
本荘市泉流寺にて50回忌慰霊祭77名参加 |
|
平成17年(2005年)10月14日 |
本荘公園にて由利郷開拓団60回忌慰霊祭 |
毎年欠かさずに集会し、「思い出を語る会」として慰霊と平和を祈念してきました。
国策とはいえ、遠い大陸に夢を実現させながらも、故郷に帰らぬ人となった同志のことを、私たちは生涯忘れることはできません。総員350名であった団員も、現在、連絡が取れる方は27名になっています。本荘市の多大なお力添えを頂き、平成元年に、この公園に「満州開拓の碑」を建立することができました。この中に眠る皆さんの魂が安らかであることを、私たちは命のある限り見守っていこうと考えています。満州での苦い経験を語り継ぐことで、過ちを二度と繰り返さない確かな考えを郷土の人々に語り継ぐことを誓います。
平成17年10月14日 佐々木三郎団長長男 佐々木良三
(参考資料:「満州由利郷開拓誌」進藤孝三著)
付記:「満州開拓団」とは
昭和11年(1934年)当時の広田内閣は、満州国独立を契機に日本国との一体化を狙いとし、その狙いの達成に「五族共和」を掲げ、「満・蒙・漢・日・朝」の五民族が協力していくことを目指した。また、これに加えて、「王道楽土」をあげ、アジアの理想的政治体制を「王道」として満州国皇帝を中心に理想国家の建設を望んでいた。一方、当時の日本国内は、貧困な農村住民、都市部における失業労働者の増加を解消する手だてとして、大陸への大移民計画を構想した。それが、「満州開拓団」の胎動である。
この政策を分析すると、第一の狙いは、世界恐慌や凶作で弱まる国内の消費人口をスリム化することであり、「口減らし」の国家レベルでの対策であったと言えよう。第二の目的は、次第に軍国主義の思想に導かれていく日本は、世界からも孤立することを察知し、戦時体制下の食料供給地に満州国移民を考えた。第三にはソ連との関係の悪化が予測され、1919年に設置した、関東軍(中国関東州と満州鉄道を警備する日本陸軍部隊)の弱体は目に見えており、どうしてもソ連との国境を補強するために、国境付近に開拓団を送り込み、その防波堤とすることを狙いとしていた。 昭和20年(1945年)8月13日、我が由利郷開拓団に突如として告げられた「避難せよ!」の命令まで、私たちには何一つ情報がなく、終戦になることも予想していなかった。ただ不思議なことに、日本の将校等があわただしく馬に乗って駆けていくのを目にしている。「日本は戦争に勝った!」といって逃げていった将校もいたという。終戦と同時に、守るべき軍隊もおらず、ソ連軍の機関銃の砲火があびせられ、日本軍に苦しめられた中国人のうらみにさらされたのは、逃げ遅れた開拓団である。
満州国に移民した開拓団員は32万人と言われている。あくまでも日本人としてのほこりと報国の精神に支えられた人達である。団の周りには、クリーク(深く溝を掘って襲撃を防ぐ)と城壁を築き、日夜機関銃を持った番人が警戒し、毎朝、祖国日本の方向に向かって国旗を掲揚した。勿論、日本国籍のままで、その生活も日本人コミュニティの枠組みの範囲を出ることはなかった。現地人から見たら、土地は奪われるし、機関銃をもって勝手気ままに振る舞う暴力団的民族に見え反感や敵意を抱くのは当然であろう。終戦と同時に現地人の怒りは日本人への襲撃に変わり、由利郷開拓団もその犠牲になった。ソ連兵の暴行、現地人の襲撃にさらされ、八方塞がりの開拓団には集団自決の道を選ぶしか方法がなかった団も多数あったと聞いている。子どもが人身売買された例は事実で「女の子は500円、男の子は300円(満州回顧録より)」であった。私の場合は、新京(長春)で声をかけられ、「ショーハイイーパイカイチェン(おまえは百円)」といつも勧誘されていた。当時、「ポーミーマントウ」トウキビの饅頭が1個5円だった。
開拓と報国の夢を抱き自決した人11,500人。開拓団員の現地での死亡者78,000人といわれている。我が開拓団も「新京」南大房身での冬越しは地獄を絵で描いたようなすさまじさではあったが、「何時かは日本に帰る」という信念で、一日一日の命をつなぐことに懸命であったのが幸いした。秋田県からは44開拓団、5,657人(義勇隊を含む数「満州由利郷開拓誌」より)が派遣され、1,463名が命を失い、734名が未帰還者として、昭和24年(1949年)3月に報告されている。
石碑12「満州開拓の碑」の位置
このページに関するお問い合わせ
教育委員会本荘教育学習課
由利本荘市上大野16 由利本荘市市民交流学習センター内
電話:0184-22-0900 ファクス:0184-24-2714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。