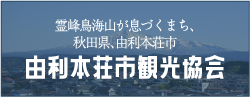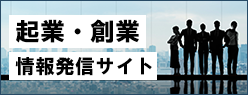施政方針(令和7年第2回由利本荘市議会定例会)
令和7年第2回市議会定例会(令和7年5月16日開催)より

本日、開会致しました第2回市議会定例会におきましては、6月補正予算を提案させていただいたところでありますが、市長選挙があり、当初予算が骨格予算となったことを踏まえ、当初予算を合わせた令和7年度の市政運営につきまして、その基本的な施政の概要について述べさせていただきます。
昨今の本市が置かれている状況を見ると、人口減少、頻発化・激甚化する自然災害の発生、急速に変化を遂げる社会経済情勢への対応など市民生活に関連する数多くの課題に直面しております。
人口の推移において、自然動態では、出生数が、コロナ禍での婚姻数の減少、晩婚化や未婚化などライフスタイルや価値観の変化などさまざまな要因を背景に減少傾向にあり、特に、死亡数につきましては、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となることもあり、引き続き増加の傾向をたどると見込まれております。
一方、社会動態では、高校卒業後の学びや仕事などの進路を市外に求める傾向が強く、転出超過となっておりますが、そうした若者が、卒業、転職、結婚など、ライフステージの節目で本市を仕事や生活の場として選択されるために、どのような施策展開が求められるのか、今後、見定めなければならない重要なテーマであると考えております。
また、性別ごとに見ても、男女ともに、転入転出の差は少しずつ縮小しており、特に男性は、令和5年には転入超過となり、中学生の年代から地域企業の良さを認識できる機会を設け、地域の企業と一体となった取り組みなどの効果が出始めたものと捉えており、将来の人口減少の改善につながる明るい兆しになればと期待しているところであります。
次に、自然災害につきましては、昨年は、石川県能登半島での震災や豪雨被害に加え、宮崎県日向灘でも強い地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報の発令に至るなど、全国的に災害の頻発化・激甚化は、年々、度を強めているように感じられる状況にあります。
そうした中、昨年7月には、本市でも、これまで経験したことのない豪雨に襲われ、多くの住家が浸水などの被害を受けたほか、農作物や農業用施設、日常生活に欠かせない道路をはじめとしたインフラ施設にも甚大な被害が発生いたしました。
さらには、相次ぐクマの市街地への出没などもあり、これまでにない場面で、自然の猛威にさらされるなど、今後は、想定を超える事態に対しても、迅速かつ適切に対応できる準備を進めることが重要になると考えております。
国際情勢に目を向けると、ロシアがウクライナへ侵攻を始めて3年以上が経過し、終息がなかなか見通せない状況にあるほか、世界各地で戦争や紛争が勃発し、国際社会の緊張度が高まってきております。
今年1月にトランプ大統領が再び就任し、100日あまりが経過したアメリカについても、トランプ関税など、その一言一言に世界中からの注目が集まる中、我が国に今後どのような影響を及ぼすのか、国にはしっかりと情勢を見極め、適切な対応を、適切なタイミングで行っていただきたいと考えております。
国内では、食料品をはじめとした生活必需品や、原油、天然ガス、電気などのエネルギー価格が依然として、高止まりしており、とりわけ、長引く米価の高騰は、家計を圧迫し続け、国では備蓄米の放出などの対応をしているところでありますが、なかなか効果が発揮されない状況にあり、一日も早く米価抑制と米不足が解消されることを願っております。
ただ今、申し上げましたとおり、今を生きる私たちは、これまでの経験則だけで立ち向かうことの難しい課題に直面しておりますが、こうした苦境は、社会の仕組みを大きく変化させるタイミングでもあるとポジティブに捉えながら、所信表明で申し上げた3つの時流をしっかりと踏まえるとともに、今後、本市が有する豊かで広大な農地が育む多彩な作物、全国有数の再生可能エネルギー供給基地、広大な森林資源といった強みを活かし、食料、エネルギー、脱炭素という時代のニーズを先取りした成長産業の育成などに、地域の資源を最大限に活用しながら、各種施策を総合的に展開し、本市の発展、成長につなげてまいりたいと考えております。
次に地方財政を巡る状況についてでありますが、国が示した令和7年度の地方財政計画では、地方全体の収支を前年度に比べ約3兆3,700億円上回る約97兆100億円の規模としたほか、地方交付税の総額につきましては、自治体に交付する「出口ベース」で、前年度比2,904億円増、率では1.6%増となる18兆9,574億円としたところであり、また、交付税の代替財源としてきた臨時財政対策債につきましては、平成13年度の創設以来、初めて発行額をゼロとしております。
この結果、地方税や地方交付税などの一般財源総額は、交付団体ベースで前年度を1兆535億円上回る63兆7,714億円が確保され、社会保障関係経費や人件費の増加などのほか物価高が見込まれる中にあって、「こども・子育て政策の強化」などの重点項目に対する地方財政措置の拡充がなされております。
こうした地方財政全体の状況を踏まえつつ、私にとって2期目の初年度となる令和7年度の予算につきましては、「全力で災害復旧に取り組む」との思いの下、災害復旧に要する経費につきましては、その所要額を計上したところであり、一般会計総額で594億2,898万8千円としております。歳入では、市税につきましては、定額減税による減少額の縮小や個人所得の増加などを考慮し、前年度比約7億4,000万円増の約87億4,000万円、地方交付税は、前年度比約4億4,000万円増の約178億5,000万円、この他、譲与税等を含めた主要一般財源の総額を、前年度比約10億3,000万円増の約295億1,000万円と見込んだところであります。
当初予算を、義務的経費を中心とした骨格予算とし、市民の安全・安心に関する事業、総合計画などに基づく継続事業、年度当初から直ちに着手が必要な事業などを計上いたしましたが、今議会に提案する補正予算案につきましては、国の新年度予算を踏まえて対応すべき事業、新たな対応が求められる事業などを肉付けとして計上したところであり、6月補正後の取り組みを含め、重点施策とした、
1 若者・女性の地域定着回帰と切れ目のない子育て支援
2 大規模プロジェクトによる関係人口の拡大と地域経済の活性化
3 市民ひとりひとりが、住み慣れた地域で心豊かに安全安心に暮らせるまちづくり
の3つの政策分野に予算配分ができたものと考えております。
令和7年度は、人件費、扶助費や公債費の義務的経費の増加に加え、物価高騰等による固定経費の増嵩、本荘東小学校の校舎建設、災害復旧費の計上などにより、歳出総額が大きく膨らんだことから、前年度を大きく上回る多額の財政調整基金からの繰入を余儀なくされる非常に厳しい予算編成となりました。
財政状況は年々厳しさを増しており、しっかりと財政の健全性を確保しつつ、本市の持続可能性を高めていく上では、今後、これまで以上のさらなる行財政改革の取り組みが必要となることを改めて申し述べさせていただきます。
それでは、令和7年度において展開する施策の概要につきましてご説明いたします。
1つ目は、「若者・女性の地域定着回帰と切れ目のない子育て支援」であります。
2024年に我が国で生まれた子どもの数は過去最少となる約72万人で、国立社会保障・人口問題研究所が2023年に公表した将来推計人口と比較すると、国が想定しているよりも15年早く少子化が進行していることが明らかになりました。
本市においても、2024年に生まれた子どもの数は286人と市誕生以来最少となり、この現状には大変危機感を抱いております。
もとより、人口減少問題は、国の行く末に関わる重要な課題であり、地方だけの取り組みでは自ずと限界があることから、国においても、我が国の将来像や、都市と地方のあり方などについて、明確なビジョンを示し、まずは、我が国全体の人口減少に歯止めをかけるための環境整備を図っていくことが重要であると考えております。
こうした現状を踏まえ、これまで以上に、若い世代や女性の価値観を尊重し、安定して働ける職場、独身者の出会いの場、安心して子どもを産み育てることができる環境など、ライフスタイルに応じたニーズを的確に捉えた施策を展開していくことが重要であります。
昨年、次期総合計画策定の参考とするため、若者を対象としたアンケートを行ったところ、「市外で暮らしたい」理由として、「希望する進学先、仕事がある」こと、また、「本市へ戻って暮らすために重要なこと」として、「希望する職種があり、給与水準が高いこと」など、いずれも、自ら望む仕事とそれに見合う高い水準の賃金や、自分の能力を十分に発揮できるやりがいのある職業を求めていることが明らかとなりました。
こうした、若者の声に耳を傾け、都会で身につけたスキルや学びを活かして本市で働きたいというニーズに応えられる就業の場の確保とともに、起業にチャレンジできる環境を整備していくことも重要であり、「起業するなら由利本荘市で」のもと、これまで力を入れてきた若者の起業支援を含め、多様な働く場の創出につながる施策を継続して取り組んでまいります。
結婚を望む若者への支援につきましては、結婚に伴う新生活に向けた経済的負担を軽減するため、今後も、新居の家賃や引っ越し費用などを支援してまいります。
また、若者が地域で自主的にいきいきと活躍できる取り組みを支援する「プロモーション会議」につきましては、昨年度、第2期生による取り組みがスタートし、地域の枠にとらわれない広域的な7つの企画が立案され、今年度は実践の段階を迎えることになります。
加えて、第1期のメンバーによる企画も継続しており、しっかりと市内全域に定着するよう支援をしてまいります。
妊産婦や子育て世帯への支援につきましては、今年10月に母子保健と児童福祉、それぞれの専門性を活かした「こども家庭センター」を本荘保健センターに開設し、一体的な相談支援の提供を進めることとしております。
さらに、妊産婦の体調や子どもの発育など、個々の家庭の状況を踏まえつつ、保育・教育・福祉・医療などの関係する機関との連携・協働を図りながら、相談者に寄り添った丁寧できめ細やかな支援を行ってまいります。
また、国の「妊婦支援給付金」や県の「あきた出産・子育て応援給付金」に加え、第2子以降の出生に対し、市独自で行っている「子育て支援金」の給付を継続するほか、児童手当や児童扶養手当の拡充にも適切に対応するとともに、高校生までの医療費無償化を継続し、出費のかさむ妊娠期から子育て期までを経済的にもしっかりと支えてまいります。
次に教育施策につきましては、「総合教育会議」を通して教育委員会と協議を重ね、教育の現状や重要課題を共有しながら、次期総合計画と整合性のある一体的な施策の推進に向けて、新たな「教育大綱」の策定に取り組んでまいります。
具体的な教育施策につきましては、この後、教育長が教育方針で述べますが、令和8年4月に開校する本荘東小学校の建設や新山小学校の改築をはじめとする教育環境の整備を進めるとともに、「ゆりほんICT子供の学びアップデートプラン」を中心とした本市独自の特色ある教育施策を推進し、将来の本市を担う子供達の学びの充実を図ってまいります。
なお、本荘東小学校区の学童保育施設につきましては、市民交流学習センターを活用することとし、利用者の利便性確保にも配慮するとともに、周辺道路の渋滞対策なども含め、子どもたちの安全確保を最優先にしながら施設改修を進めてまいります。
2つ目は、「大規模プロジェクトによる関係人口の拡大と地域経済の活性化」であります。
本市では、鳥海ダム建設事業、洋上風力発電事業など大規模事業が同時進行しております。加えて、昨年6月には、本市沖を含む秋田県南部沖が浮体式洋上風力発電の実証事業の実施海域に選定されたところであり、本市を訪れる事業関係者や観光客など関係人口と交流人口の拡大につながる好機を迎えており、これらの大規模プロジェクトがもたらす地域経済への波及効果をより実感できるよう各種取り組みを進めていくことが重要であります。
はじめに、一番堰まちづくりプロジェクトにつきましては、351人が入居できるTDK社員寮と特別養護老人ホーム「萬生苑」の整備が完了し、現在は、本荘東小学校の建設と市道整備などが進められております。
中でも、TDK社員寮につきましては、市外出身者が数多く入居しており、本市への若者定着に大きく寄与しているほか、食堂やスポーツジムなどさまざまな機能が完備された供用棟が、地域の皆様にも利用できるよう開放されており、さらには、地域を巻き込んだイベントや活動の拠点としても広く活用され、新たなにぎわいの拠点として、今後ますます認知度が高まっていくことが期待されているところであります。
計画された施設のうち、病院につきましては、残念ながら資材高騰などにより、移転計画の中止が余儀なくされ、現在、まちづくり協議会が今後の対応方針について協議を重ねているところでありますが、引き続き、官民連携による「まちづくり」の理念を踏まえながらプロジェクトを進めてまいります。
なお、市道整備につきましては、施工時期の制約や軟弱地盤による函渠工事の遅れから「市道一番堰薬師堂線」の完成が、令和10年4月となっております。
新たな観光スポットとして期待が高まる「鳥海ダム」につきましては、昨年度から本体工事に着手されたところであり、刻々と姿を変えるダム工事の現場ならではの壮大で迫力ある眺望をインフラツーリズムの大きな魅力として売り込み、観光客の増加につながることが期待できるものであります。
また、ダム完成後には法体園地が鳥海山麓エリアの新たな観光拠点となることを見据え、「法体園地再整備計画」の策定に向け、国や県との協議を継続しながら、再整備に係る許可申請など必要な手続きを進めることとしております。
このほかの取り組みといたしましては、鳥海山周辺にある観光スポットの周遊性向上を図るため、観光アクセス道路となる市道百宅線の代替道路の整備を進めるとともに、新たに出現するダム湖と鳥海山の一望千里の素晴らしい景色を堪能できる展望スペースを観光スポットとして設置することとしております。
さらに、ダム湖に沈みゆく百宅地区の歴史を学ぶ「百宅さと歩き」と組み合わせながら、旅行者が新しい発見ができるツアーやイベントを提案し、ハード、ソフトの両面で充実を図ってまいります。
次に、本市沖で進められている洋上風力発電事業につきましては、現在、事業者において事業の再評価が行われているところであり、夏頃には対応方針が示される予定とされ、その動向を注視してまいります。
なお、地元企業がこの事業に参画するためには高い水準の技術や資格が求められることから、そうした人材教育に前向きで意欲的な地元企業に対しては、積極的な支援を考えており、人材確保を含む支援措置など、事業者のニーズに沿った支援等を行ってまいります。
また、洋上風力発電施設の建設海域に最も近接している本荘港の有効活用に向けてバックヤード整備などにつきまして、引き続き港湾管理者である県に要望してまいります。
次に、観光振興につきましては、次期総合計画策定と歩調を合わせながら、社会経済情勢の変化や観光ニーズに対応した観光施策のマスタープランとして「観光振興計画」の策定を進めております。
この計画において、重点テーマの1つとなる鳥海山観光につきましては、環鳥海エリア全体の観光誘客力の向上を図るため、本市が有する観光資源の磨き上げや新たな観光コンテンツの発掘に努めるほか、市境や県境を越えた連携により、一体的な情報発信を強化しながら、新たな観光コンテンツの創出などにも目を向け「鳥海山を核とした広域観光振興」に取り組んでまいります。
広域観光の取り組みの1つである「鳥海山・飛島ジオパーク」につきましては、本年度から「ユネスコ世界ジオパーク」の認定に向けた具体的な取り組みがスタートすることから、ジオパーク推進協議会を中心とした4市町の連携強化を図り、教育、地域振興等への活用を通した自然と人間との共生や、持続可能な開発の実現に向けた活動を引き続き推進してまいります。
コロナ禍以降、戻りつつあるインバウンドへの取り組みにつきましては、1月から3月までの四半期の訪日客が1,000万人を超え、四半期では過去最多となりました。
一方で、人気観光地へのオーバーツーリズムが顕在化するとともに、特に、地方では特色のあるコンテンツの有無によってインバウンド需要に偏りが見られるようになってきております。
本県では、秋田空港と台湾・桃園国際空港を結ぶ定期チャーター便が好調を維持し、台湾からの訪日客が増加していることを踏まえ、本市といたしましても、この流れを好機と捉え、モノ消費よりコト体験を重視した観光プログラムの創り上げとともに、「訪日観光推進補助金」を活用した訪日客の誘客促進に努めてまいります。
あわせて、本市の特産品である市産米や秋田由利牛などをPRしながら、「食の体験」を観光コンテンツとしてインバウンドの取り込みに向けアピールしてまいります。
多世代交流と木育推進の拠点である「鳥海山 木のおもちゃ館」と「あゆの森公園」につきましては、さらなる利用促進を進めるとともに、「本荘こけし」をはじめ市産材で製作する木工ブランド品の普及・活用などの木育事業を推進してまいります。
芸術文化の振興につきましては、市民の主体的な活動への支援と、優れた芸術に触れる機会の創出に努め、本市の特色ある文化を生かした事業を展開するとともに、建設から14年を迎える文化交流館「カダーレ」につきましては、大ホールの設備改修を図りながら、芸術文化拠点としての環境の維持向上に努めてまいります。
生涯スポーツの振興につきましては、市民1人ひとりが、プロスポーツチームによるスポーツ教室などを通して、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現と健康長寿に結びつく取り組みを進めてまいります。
また、競技スポーツの振興につきましては、指導者の育成を図りながら競技力の向上を推進するとともに、スポーツ少年団の活動支援、中学校の部活動の地域移行へ向けた支援を充実させてまいります。
全国規模の大会やスポーツ合宿等の誘致を推進する上で、安全で快適なスポーツ施設の利用環境の整備が重要であることから、「スポーツ振興計画」に基づき改修等を進めることとし、今年度は利用頻度が高く、改修要望の強い本荘由利総合運動公園テニスコートの改修を行うなど、スポーツを通した交流人口の拡大に向けた環境づくりに努めてまいります。
本年も7月に氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」の公演が予定されているほか、県内唯一の開催となる「NHKのど自慢」、さらには、秋田県内では7年ぶり、本市では初の開催となる「令和7年 夏巡業大相撲由利本荘場所」といった、市誕生20周年記念に花を添えるイベントの招致が叶い、開催が決定されたところであり、今後も多様なイベントを通して、交流の拡大による地域経済の活性化と賑わいの創出につなげてまいります。
本市産品の売り込みにつきましては、本市の良食味米と、それにマッチする食にスポットを当て、ふるさと納税登録事業者の皆様とともに、都市部で開催する市独自フェアや、大手民間企業が主催する大規模イベントなどにより、積極的にPRを行いながら、ビジネスチャンスの創出を図るほか、交流機会の拡大や、ふるさと納税の寄附額増加につなげてまいります。
本年度からの新たな取り組みとして、都内の小学校に通う親子を対象に市産米を使った食育・地方交流授業を開催し、その美味しさや食文化に触れていただくとともに、良質な米を育む本市の自然環境や米づくりの現状、農家の思いなどについても紹介することとしており、こうした取り組みにより本市の認知向上と、新たな関係人口の創出につなげてまいります。
ふるさと納税につきましては、昨年度、本市の人気返礼品である米が、大雨災害による減収や取引価格の高騰等の影響を受け、提供可能な量が大幅に減少したことなどもあって、残念ながら寄附額は約4億1,000万円に止まったところであります。
主要な返礼品である米の市況は、今年度も引き続き厳しいものと見込まれますが、既存登録事業者や市内の米農家、農業法人等と連携を図り、返礼品確保に努めるとともに、米以外の既存返礼品の拡充や新規事業者の発掘を進め、寄附額「5億円」の達成を目指してまいります。
さらに、企業版ふるさと納税につきましては、税制改正により、3年間延長されたところであり、新たに、寄附を希望する企業と本市を結びつけるマッチング業務を民間事業者に委託し、より多くの企業から本市の取り組みへの支援を促し、新たな寄附金の獲得へと結びつけてまいります。
移住・定住につながる取り組みにつきましては、未就学児とその家族を対象とする「保育園遊学」を、えみの森と石沢保育園の2園で継続して実施するほか、新たに、就学児童・生徒とその家族を対象に、東由利小学校と東由利中学校において「教育遊学」を試験的に実施してまいります。
さらに、高校生を対象に「地域みらい遊学」を、矢島高校との連携のもと、推進したいと考えており、県外からの入学生が、住民との交流を図りながら地域で暮らし、3年間にわたり学びを深めようとすることを目指し、今年度は、高校や地域と連携しながら、来年4月の入学生募集に向けて、取り組めるよう必要な準備を進めてまいります。
こうした新たな取り組みとともに、従来から実施している、県外の大学生等を対象とした保育士インターンシップについても、「みらいデザイン遊学」として刷新するなど、未就学児から大学生までの、将来を担う幅広い世代を対象とした一連の事業を、「ゆりほん保育・教育遊学」として総合的に展開してまいります。
本市の主要産業である電子部品デバイスを中心とした製造業は、堅調な業績で推移していると伺っており、引き続き、企業の用地購入に対する補助制度の拡充や、初期費用の負担軽減などにより、生産性の向上や規模拡大、異業種へのチャレンジなどの取り組みを促すとともに、企業誘致につきましては、これまで重点的に支援してきた製造業、研究施設等に、新たに宿泊業を加え、大規模プロジェクトに関連した誘客と合わせ、観光関連でのさらなる関係人口拡大に対応していきたいと考えております。
次に農業につきましては、昨年の豪雨が、水田や水路などの農地・農業用施設に甚大な被害をもたらしたところであり、復旧に向け、工事の発注手続を急いでいるところであり、特に、本年度は、復旧工事がピークを迎えることを踏まえつつ、これまで経験したことのない災害規模、件数であるほか、入札不調も散見される状況にはあるものの、全力で復旧事業に取り組んでまいります。
復旧事業を円滑に進めていく上で何よりも、関係する農家や土地改良区などの関係機関と連絡調整を十分に図ることを目指し、農家の皆様が一日も早く営農再開ができるよう全力で取り組んでまいります。
また、令和4年に制定された「みどりの食料システム法」においては、国として2050年までに化学肥料の使用量を30パーセント低減する目標が定められたところであり、本市においても、これらの目標達成に向け、環境負荷低減のため、地域資源である堆肥やもみ殻を活用した循環型農業への取り組みを進めてまいります。
米政策につきましては、令和6年産米が、大幅な価格上昇となったものの、資材価格等が高止まりしていることから、生産者の所得確保までには至っていないのが実情で、依然として農業経営は厳しい状況が続いておりますが、水田活用米穀や高収益作物へのさらなる転換を促しながら、需要に応じた「売れる米づくり」を推進してまいります。
米は我が国で自給自足が可能な数少ない農作物であり、国内の米不足解消や関税交渉の取引材料として、安易に輸入枠を拡大し、安価な外国産米に頼ることは、国内の米の供給力を脆弱化させることに繋がりかねません。
一方で、高騰を続ける米価は、家計に大きな負担となっており、今後、米離れが起こることが懸念されることから、こうした米を取り巻く情勢の変化に、米産地として、今後も注視してまいります。
園芸作物につきましては、引き続き「シャインマスカット」、「タマネギ」などの高収益作物の導入を推進するとともに、「秋田鳥海りんどう」や「アスパラガス」などに対する栽培促進や規模拡大への支援の充実を図りながら、複合型の農業生産構造への転換を促してまいります。
畜産につきましては、飼料価格の高止まりを踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、緊急的に肉用牛、乳用牛、養鶏の各農家の経営支援を行うことにより、安定した生産体制の構築に向け取り組むとともに、秋田由利牛の振興を図るため、関係機関と連携した、販路拡大とイベント等でのプロモーション活動に注力してまいります。
担い手の確保・育成につきましては、スマート農業をはじめとする省人・省力化につながる農業機械の導入を支援するとともに、将来の農地利用を定めた地域計画について、地域との話し合いを通して、より実効性のある計画となるよう適宜見直しを行いながら効率的な農地の利活用を促進してまいります。
また、新規就農者に対しては、就農前の技術習得に係る研修支援や、就農時の施設整備や経営開始資金の支援により、力強く就農を後押しするとともに、農業体験や移住就農などの本市の魅力を効果的に発信し、農業人材確保と定着を進めてまいります。
農業生産基盤整備につきましては、本荘地域 松ヶ崎地区など3地域の事業を推進するほか、鳥海地域 笹子地区の事業採択に向けた調査・計画策定に取り組んでまいります。
また、現在、未利用で決壊した際に、重大な被害を及ぼす恐れのある防災重点ため池につきましては、計画的に廃止を進めるほか、日本型直接支払制度による地域の共同活動や農業生産活動への支援を継続してまいります。
森林・林業につきましては、引き続き、森林環境譲与税を活用し、民有林整備を推進するとともに、急拡大している松くい虫被害対策を強化し、森林が持つ多面的な機能の維持・増進を図り、地域林業の振興に努めてまいります。
また、適切な森林管理により吸収された二酸化炭素量を国がクレジットとして認証する「J―クレジット」の制度を市有林で活用する取り組みを進め、クレジット収入を林業経営基盤の強化に充てるとともに、地球温暖化対策にも活用してまいります。
水産業につきましては、機能保全事業を計画的に推進し、西目及び道川漁港施設の長寿命化を図るため、航路や泊地などの浚渫を行うなど、漁業活動に支障が生じないよう、適切な漁港管理に取り組んでまいります。
3つ目は、「市民ひとりひとりが、住み慣れた地域で心豊かに安全安心に暮らせるまちづくり」であります。
住み慣れた地域で健康で安全・安心に過ごせるよう、人と人の結びつきを大切にした地域コミュニティの活性化に取り組むとともに、医療、買物など日常生活を不自由なく過ごすことができる社会インフラ基盤の維持や地域公共交通の充実を図ってまいります。
さらに、高齢者や障がいを持つなど社会的に弱い立場の皆様に寄り添い、安心して暮らすことのできる各種取り組みを進めてまいります。
健康づくりにつきましては、「歯と口腔の健康づくり事業」として歯科健康診査に新たに取り組むなど、日々の健康管理や食生活の改善、運動の習慣化など健康づくりに資する施策を総合的に推進し、健康寿命の延伸を図るとともに、命を支える自殺対策の取り組みを強化してまいります。
地域医療につきましては、救急告知病院への運営費支援を継続するとともに、安定的に医師・看護師が確保できる施策を推進することにより、市民の皆様が安心して診療を受けられる充実した医療提供体制の維持に注力してまいります。
地域福祉につきましては、ひきこもり等の複雑化・困難化しつつある家庭課題への伴走型の支援や、障がい者の地域生活支援のほか、成年後見制度を活用した権利擁護支援の充実の確保に向け、多職種による連携をより一層深化させるとともに、地域のニーズをきめ細やかに汲み取り、適切かつ柔軟な福祉サービスの提供に努めてまいります。
高齢者福祉につきましては、第9期高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるよう、介護予防、認知症対策等の充実・推進に取り組んでまいります。
加えて、今後も増加が見込まれる介護サービス需要に対応するため、関係機関との緊密な連携のもと、今年度から市が単独保険者となったことを踏まえつつ、介護保険事業の安定した運営に努めてまいります。
次に防災対策についてでありますが、全国各地で地震や大規模な山林火災が相次いで発生し、局地的な豪雨・豪雪など、全国的に自然災害が頻発化・激甚化する中、私たちが忘れてはならないのが、昨年7月に市内各地に大きな被害をもたらした豪雨災害であります。
今後の防災対策に活かすため、昨年、市では「豪雨災害対応検証委員会」を設置し、災害発生後の一連の対応について検証してきたところであり、その検証結果を踏まえ、より迅速・的確な対応を行うため、総合的な訓練を実施するなど、関係機関との連携を深め、災害対応の精度を高めてまいります。
さらに、町内会など地域コミュニティを対象とした「むこう三軒両隣・たすけあい事業」や「自主防災組織活動促進補助金制度」などにより、自助・共助意識の一層の醸成と地域防災力の向上を図るほか、担当職員が積極的に自主防災組織等の総会や出前講座などに足を運び、市民の皆様に向けて、想定される災害の種類や危険箇所、災害発生時の基本的行動などの周知を図ってまいります。
また、緊急時の情報伝達手段を強化するため、新たに、スマートフォンを持たない方などを対象に、固定電話への一斉架電やファクスで災害避難情報等を配信するサービスを開始するほか、防災行政無線や秋田県総合防災情報システムの改修を進め、引き続き消防・防災メールなどへの登録を呼びかけてまいります。
消防防災体制の維持強化につきましては、消防車や救急車の更新と耐震性貯水槽の整備、地域の実情を熟知し大規模災害時に大きな役割を果たす消防団員の確保と消防団車両や小型動力ポンプの更新など、消防施設や装備の充実を図り、消防力の強化を図ってまいります。
昨年の豪雨災害からの道路関係の復旧につきましては、冬季間でも通行を確保しなければならない路線を、優先して工事を進めてきたところであり、今年度は発注のピークを迎えることとなりますが、総力をあげて復旧に取り組んでまいります。
この度の豪雨災害の経験を踏まえ、地球温暖化などによる頻発化に備える上で、これからの大雨にも耐えうる、単なる原状回復に留まらない、さらなる施設の強靱化を図ることが重要であると考えられることから、特に、大雨の際に大きな影響が懸念される子吉川への対策として、洪水調整機能の要ともなる鳥海ダムの早期完成や河道掘削、堤防の嵩上げなどを含めた強化策が重要であり、その推進について関係機関に強く要望してまいります。
道路整備につきましては、一番堰まちづくりエリアと国道107号、108号を結ぶ 新たな幹線道路の役割を果たす「市道薬師堂25号線」を令和8年4月の本荘東小学校開校に合わせ整備するほか、児童生徒の通学路となる「市道鶴沼薬師堂線」の安全で円滑な通行の確保に向け、道路拡幅と歩道設置を行うこととし、その用地取得と建物補償を進めてまいります。
羽後本荘駅東口へのアクセス道路である「停車場東口線」につきましては、概ね移転補償が終了し、本格的に工事に着手する予定であり、駅の東西間を往来する自転車・歩行者の安全・安心の確保を最優先に、羽後本荘駅及び周辺施設の利用拡大につながるよう取り組んでまいります。
また、市道や通行止めで市民の皆様にはご迷惑をおかけした由利橋をはじめとする橋梁などの施設につきましては、長寿命化修繕計画に基づき、安全性の確保を優先しながら、持続性の向上につながるメンテナンスに取り組んでまいります。
住宅政策につきましては、「住宅リフォーム資金助成事業」や「木造住宅耐震診断支援事業・耐震改修補助事業」を継続し、良好で安全・安心な住環境の向上と地域経済の活性化を図ってまいります。
水道事業につきましては、鳥海ダム建設に伴う事業の一環として、百宅地区の水道施設整備に係る実施設計に、令和8年度の完了を目指し取り組んでまいります。
また、昨年度に引き続き、一番堰まちづくり事業区域に給水できるよう配水管を整備するほか、既存管等の更新工事を継続するなど、水道管網の整備を進めることにより、今後も安全な水道水を安定供給できるよう努めてまいります。
下水道事業につきましては、処理施設における維持管理経費の軽減を図るため、昨年度に引き続き、西目処理区の本荘処理区への統合を進めるほか、岩野目沢処理区を隣接する葛岡・新田処理区へ統合してまいります。
今後も、処理施設の統廃合や既存施設の長寿命化などに取り組むことにより、施設の維持管理費の軽減を図り、持続可能な事業運営に努めてまいります。
ガス事業につきましては、昨年度に引き続き、一番堰まちづくり事業区域にガス管及び整圧器を整備し、本荘東小学校へ都市ガスを供給できるよう手当てするとともに、開発地における熱源利用の選択肢を拡げ、将来需要への対応と周辺エリアも含めた都市ガスの安定供給につなげてまいります。
市民の皆様の移動手段である地域公共交通につきましては、路線バス等の慢性的な運転士不足といった課題を抱えておりますが、循環バス等の中心市街地からの延伸・拡大を求める多くのご意見に対応するため、新たに、実証試験としてAIによるオンデマンド交通を導入し、その効果や課題を洗い出し、持続的な交通体系の整備について検討してまいります。
今後とも、地域間を結ぶ幹線路線である羽後交通の路線バスや鳥海山ろく線の維持確保を図るとともに、地域内路線であるコミュニティバスにつきましては、実情に応じた運行形態への再編を進めてまいります。
新ごみ処理施設整備事業につきましては、アクセス道路の法面補強工事を進めるほか、着手を延期した本体工事に向け、引き続き、整備内容や事業者選定方法などを検討し、事業全体の効率性を高めるよう努めてまいります。
地域の元気創出や課題解決に向けた取り組みにつきましては、地域の特性を踏まえた民間団体による自主的な取り組みを支援する「地域づくり推進事業」や、「ともしび元気プログラム補助金」を継続し、地域の活力向上と元気の創出につなげるとともに、地域を支える人材育成とマンパワーの向上を図ってまいります。
さらに、8地域において独自の事業を立案し実践する「元気な地域チャレンジ事業」につきましては、地域の賑わいづくりなど、地域の特色を活かした施策を進めてまいります。
今年度は、これまでご説明いたしました3つの柱に基づく施策、事業のほか、本市の将来を見据えた次期総合計画を策定するとともに、持続的に行政サービスを提供できるよう業務の見直しと組織機構の再構築と合わせ、公共施設の適正配置を含む、行財政改革大綱を策定し、効率的な行財政運営の体制確立に向け努めてまいります。
総合計画「新創造ビジョン」につきましては、本年度で最終年度を迎えることから、現在、来年度から始まる次期総合計画の策定作業を鋭意進めているところであります。現行計画の取り組みを振り返り、市が置かれた現状を的確に分析し、これから為すべきことを明らかにしながら、市の10年先の将来像を構想しながら策定に取り組んでまいります。
具体的な取り組みにつきましては、分野ごとの基本政策に加え、「ゼロカーボン」、「デジタル化」、「連携協働」などを、基本政策を横断する取り組みとして位置づけ、「人口減少を前提としながらも市民が心豊かに暮らせるまちづくり」を目指して市の進むべき方向性を明らかにしてまいります。
総務省が先に公表した昨年10月時点での人口推計では、人口減少率が1パーセント以上の都道府県は、コロナ禍前の2019年と比較すると9県から18県に倍増しており、地方の人口減少が一段と加速しております。
本市でも、市誕生以来、20年が経過し、地域によっては4割以上も人口減少が進むなど、今後の行政運営に大きな影響を及ぼす重要な課題であると認識しているところであり、施設の統廃合、組織や業務のあり方をこれまで以上に考えていく必要があります。
行政サービスの質を落とすことなく、市民が住み慣れた地域で心豊かに、安全安心な生活を営むことができるよう、将来をしっかりと見据えて第5次行政改革大綱策定を進めるとともに、立ち止まることなく改革を進め組織機構の再編を含む行財政改革について、市民の皆様の協力もいただきながら、本市の持続可能性が高められるよう積極的に進めてまいります。
また、行財政改革を進める上で、すべての施策を横断的にカバーする視点となるデジタル化についても力を入れ、市民の皆様の利便性向上と業務の効率化に結びつくDXを更に加速して推進してまいります。
地球温暖化対策につきましては、令和5年に宣言を行った「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、各施策に脱炭素社会の実現に資する取り組みを盛り込んでいくほか、市民の皆様や産業界、各種団体等と連携しながら、温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みを推進してまいります。
また、「OPENトーク」をはじめ、さまざまな機会を通して、市民の皆様から頂いた声を大切に受け止め、市政に反映できるように努めてまいります。
特に、市外の出身者が多い県立大学の学生や、将来を担う高校生などの若い世代の声にも積極的に耳を傾けてまいりたいと考えております。
それと同時に、市公式ホームページを情報発信の中核としながら、LINEやX、ユーチューブなどのSNSにつきまして、それぞれの媒体の特徴を踏まえながら積極的に活用することにより、きめ細やかな情報発信を行い、市内外に本市の魅力が広く伝わるよう努めてまいります。
以上、今後の施政の方針について述べさせていただきました。
私の市長就任1期目を振り返ると、前半は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止などの市民の命を守る取り組み、コロナ禍によってダメージを受けた家計や地域経済の立て直しに努めてきたところであります。
コロナ禍が終息した後は、これまで例を見ない自然災害への対応に追われたところであり、常に市民の安全・安心を確保することを第一に考えて行動してきたところであります。
一方で、この間も、希望のある市勢発展を想い描きながら、未来への投資を惜しまず、発展や成果につながる多くの希望のタネを蒔いてまいりました。
市政運営の第2章をスタートさせるにあたって、これまで蒔いてきたタネが健やかに育ち、大きな花を咲かせるためにも、現在、大変厳しい財政状況にあることを踏まえ、将来に向けた投資を果敢に行うことができるよう、これまで以上に行財政改革を進めなければなりません。
それは、希望ある未来に向け、持続的に市政を発展させるための「産みの苦しみ」であり、これからも市民の皆様とともに、これまでの発想にとらわれない新しい着眼による、由利本荘市が成長する姿を創造しながら、山積する課題に対して、「オール由利本荘」で果敢にチャレンジしてまいりたいと考えておりますので、議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部秘書課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6203 ファクス:0184-23-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。