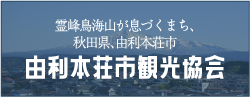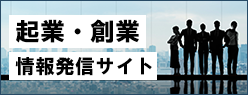国民健康保険税
国民健康保険税(以下「国保税」と表記します)は、誰もが安心して医療を受けられるための国民健康保険(以下「国保」と表記します)の制度を支える大切な財源です。 国保税は、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(以下「擬制世帯主」と表記します)となります。 40歳から64歳までの国保加入者は、介護保険に係る納付金分を合わせて、国保税として納めていただきます。65歳以上の方の介護保険料については、下記の関連情報のページをご覧ください。 国民健康保険税とは
病気やけがの治療にかかる医療費は、”病院の窓口で支払う自己負担分”と、”国や県の負担分”、そして、皆さんが納めている”国保税”で支えられています。
健康で明るい生活を送ることができるよう、国保制度を正しく理解し、加入者の皆さんの力で守っていきましょう。1.納税義務者
2.国保と介護保険
国保税は、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合算額です。 当年4月から翌年3月分を当該年度の国保税として、当年4月1日の加入状況に応じ、前年の所得等により計算します。 現年度税率等については、下表のとおりです。 税率 所得割 均等割 平等割 課税限度額 22,500円 26,000円 66万円 11,800円 なし 26万円 14,000円 なし 17万円 ※税率や各金額については、見直しにより変更となる場合があります。 国の法改正に伴い課税限度額が引き上げになりました。 (基礎分 65万円→66万円・後期高齢者支援金分 24万円→26万円) 課税限度額を超えた部分は超過額として課税されません。 課税の基礎となる所得とは、総合課税の対象となる所得、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得等の合計額です。 令和7年7月31日(木曜日) 【特別徴収(年金からの天引き)で納めていただく方】 平成20年度から、国保税の特別徴収の制度が始まりました。老齢年金等を受給している65歳以上の国保加入者は、次の全ての要件に該当した場合は原則として特別徴収の方法によって納税することになっています。 なお、上記要件を欠いた場合や年度途中で税額が変更となる場合は、当該年度の特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わることがあります。 特別徴収を希望されない場合は、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。 世帯主または擬制世帯主と、その世帯の国保加入者の所得金額の合計が下記基準に該当する場合、1人あたりに一律課税される”均等割”額と、世帯に一律課税される”平等割”額が軽減されます。 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 43万円+30万5千円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) 以下 注1:給与所得者等とは次のいずれかに該当する方 注2:被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人も含む 後期高齢者医療制度創設に伴い、75歳以上の方が後期高齢者医療制度(後期)に移行しても、国保税が急激に増えることがないように、一定期間、国保税が次のように軽減されます。いずれの場合も申請の必要はありません。 【国保から後期への移行に伴う軽減】 75歳以上の方が後期に移行したため、国保の加入者が1人となる場合、最長8年間、平等割が減額されます。最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。但し期間中に他の世帯員の方が国保に加入した場合は終了します。 【被用者保険の被扶養者であった方の減免】 75歳以上の方が、社会保険などの被用者保険(注1)から後期に移行することによりその扶養になっていた65歳から74歳までの方(旧被扶養者といいます)が、国保の資格を取得した場合には、資格取得時から次のような軽減が受けられます。 注1 被用者保険とは、全国健康保険協会や企業の健康保険組合、公務員等の共済組合、またはそれらの任意継続(国保組合は除く) 倒産、解雇等により雇用保険受給者となった国保加入者は、離職の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定する軽減が受けられます。この軽減には申請が必要です。3.税率
税率等と課税限度額
4月1日以降に加入者の数が変わった場合は、月割りで計算し直します。
基礎(医療)分
8.60%
後期高齢者支援金分
2.70%
介護納付金分
2.80%
4.納期・納付方法
納税通知書は7月中旬にお届けします
期別
納期限
第1期
第2期
令和7年9月1日(月曜日)
第3期
令和7年9月30日(火曜日)
第4期
令和7年10月31日(金曜日)
第5期
令和7年12月1日(月曜日)
第6期
令和8年1月5日(月曜日)
第7期
令和8年2月2日(月曜日)
第8期
令和8年3月2日(月曜日)
ただし、変更には一定の条件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。5.軽減制度
低所得世帯の軽減
申請の必要はありません。
軽減割合
軽減の基準となる所得金額
7割軽減
5割軽減
2割軽減
43万円+56万円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) 以下
後期高齢者医療制度創設に伴う減額
雇用保険特定離職者等の軽減
詳しくは下記の関連情報を確認してください。
令和5年11月以降に出産した(または出産予定)被保険者の出産日の属する月を基準として、単胎で最大4カ月分・多胎最大6カ月分の所得割額と均等割額を免除します。世帯主課税のため、世帯に他の被保険者がいる場合は、年税額のうち対象被保険者の免除額分が全体の税額から減額される形になります。詳しくは下記リンクをご参照ください。 令和4年4月から、国の法改正に伴い未就学児の均等割額を軽減しています。所得制限を設けず、未就学児を対象に5割軽減します。世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の均等割額の2分の1を減額します。手続きの必要はありません。 生活困窮や災害のため納付が困難な方は、申請により減免を受けられる場合があります。申請は、納期限の7日前までに印鑑と生活状況・資産状況についてわかる書類を持参のうえ、税務課または各総合支所市民サービス課で手続きしてください。出産する/した被保険者の産前産後期間の所得割額・均等割額減額制度
未就学児の均等割額軽減
6.減免制度について
注:住民票にかかわらず、原則として同居している方全員の関係書類が必要となります。
特別な事情等の申し出がないのに国保税を滞納すると、以下のような措置がとられます。納付が困難なときは早めにご相談ください。 お申込みをいただいた口座から自動的に納税できる、口座振替のご利用をお勧めします。7.納税相談について
8.納付は口座振替が便利!
手数料が不要で、納期ごとに市役所や金融機関などへ足を運ぶ必要がなく、また納め忘れの心配もありませんので、安全で便利です。
お申込みは市役所収納課、各総合支所市民サービス課、および市内金融機関の窓口で。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。