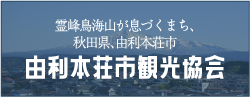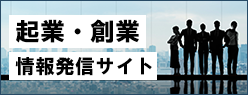健康づくりのための睡眠ガイド
良い睡眠とは
睡眠による休養感が大切

適切な睡眠の目安として、朝目覚めたときにしっかりと休まった感覚(休養感)があることが重要です。睡眠休養感の低下は、体や心の不良な健康状態とかかわることが明らかにされているからです。
睡眠休養感を高めるために
- 適度な睡眠時間を確保する
- 睡眠を妨げる要因、睡眠にかかわる習慣的な行動や環境を見直す
働く世代にとって必要な睡眠時間は最低 6 時間
働く世代は慢性的に睡眠が不足しがちです。睡眠不足は、肥満や高血圧、うつ病などのさまざまな疾患リスクの増加と関連することがわかっています。休養感のある睡眠のためには、1日に少なくとも6時間以上の睡眠を確保することが大切です。
高齢者は 8 時間以上の長寝に注意する
必要な睡眠時間は加齢とともに減少します。また、床上時間が8 時間以上になると死亡リスクが上がるというデータがあります。休養感のある睡眠のためには、日中は活動的に過ごし、昼と夜(活動と休息)のメリハリをつけることが大切です。
こどもは年齢にあわせた睡眠時間を確保する
こどもの睡眠は脳と身体を成長させる役割があります。また、生まれてから発達段階が進むに伴い、睡眠・覚醒リズムが劇的に変化すると同時に睡眠習慣も変化する時期のため、成長にあわせた工夫が必要になります。1〜2歳児は11〜14時間、3〜5歳児 は10〜13時間、小学生は9〜12時間、中学・高校生は8〜10時間の睡眠時間の確保が推奨されています。
良い睡眠のための工夫
寝室の環境を整える
寝るときの環境で重要なことは『光・温度・音』です。良い睡眠のために、寝室の環境を見直しましょう。
| 光 | 朝日を浴び、日中は明るく、夜は暗い環境を心がけることで体内時計が整いやすくなります。朝はカーテンを開け、室内に光を取り入れましょう。夜は室内照明を弱くして光の量を減らし、できるだけ暗い環境で眠りましょう。 |
|---|---|
| 温度 | 室内は暑すぎず寒すぎない温度を心がけましょう。夏はエアコンなどを活用し、室内を涼しく保つことが重要です。冬はトイレに行くときや早朝の極端な寒さによる健康リスクを避けるため、18℃を下回らないよう室温を調 整しましょう。就寝1~2時間前にお風呂に入り一度体温を上げることで、眠りにつきやすくなります。 |
| 音 | 騒音は寝付きを悪くしたり、睡眠の維持を困難にする可能性があります。できるだけ静かな環境で眠りましょう。 |
スマートフォンの使用を控える
睡眠の1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控え、室内の照明を半分にするなど明るさに気をつけましょう。寝室にスマートフォンなどを持ち込まない、通知を切る、寝る直前に返信をしないなどの習慣化が重要です。
日中の運動・身体活動を増やす

日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝付きが促され、中途覚醒が減り、睡眠の質が高まります。重要な点は「運動の習慣化」。習慣的に運動している人の70%以上は睡眠の質が良いことがわかっています。
こどもと働く世代は中~高強度の身体活動、高齢者は低~中強度の身体活動が睡眠不足のリスクを減らします。寝る前2~4時間の運動はかえって目を覚ますので避けましょう。
| 低強度 | 中強度 | 高強度 |
|---|---|---|
|
|
|
朝食を抜かず、寝る直前の食事は控える
朝食を抜くと、体内時計は後ろにずれてしまい、寝付きが悪く、睡眠不足になりやすくなります。しっかりと朝食をとるようにしましょう。また、睡眠直前の2時間以内に食事をとると、睡眠の質を低下させる可能性があります。なるべく決まった時間に食事をするよう心がけましょう。
嗜好品とのつきあい方を見直す

寝る前にリラックスすることは寝付きをよくするために効果的です。ただし、飲酒や喫煙などの嗜好品は使用する量やタイミングを誤ると、かえって睡眠を悪化させ、健康を害すことがあります。
- 過量なカフェイン摂取を控える
- 晩酌は控えめにし、寝酒はしない
- 喫煙をしない
眠れないときは

感情が高ぶった状態のまま眠ることはできません。感情をしずめ眠りに適した状態にするために、就寝前に行う自分に合ったリラックス法を持つことが大切です。こうしたリラックス法を使っても寝付きが悪く20分以上眠れない場合は一度寝床を出て、暗い場所でリラックスして過ごし、無理に寝ようとせず、眠気を感じたら寝床に戻りましょう。
リラックス方法の例
- アロマ
- アイマスク
- 静かな音楽を聴く
- 入浴、足湯など
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。