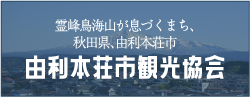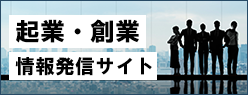「わたしから市長への提案」に対する市の対応・方針(令和6年度受付分)
- リユースシステムについて
- 東由利健康増進センターのトレーニングルームの、筋トレ、有酸素運動マシンの講習会やケーブルテレビでの使用方法の紹介
- ごてんまりコーナ(スペース)の設置をお願いいたします
- 事前投票所の巡回について
- 路線バスの今後のこと
- 子育てしやすい由利本荘市
- 駅前バス停にベンチを
- 歩道の設置
- 子どもたちが遊べる施設がほしい
- 由利本荘総合防災公園について
- 若者への娯楽からの街づくり
- 学校に民間の風を入れたい
- 犬と人が楽しく過ごせる町 ー地域活性を目指してー
- 野良猫対策について
- 若者世代に希望を
- Instagram等のSNSの利用状況の悪作
- 保育料を無料に
- 市営住宅等の入居者の収入上限金額について
- 菖蒲公園の移設
- 続 本荘IC付近の渋滞について
- バス通学希望者へのバス代補助制度の導入・スクールバスの導入
- 通学路の安全確保
- 熊出没多発地区における通学4km以下地区へのスクールバス運行継続を検討下さい
市民の皆さまからいただいた提案の対応・方針が決定したものから、順次掲載してまいります。
なお、提案内容については、個人が特定できる情報を削除しているほか、内容を要約している場合があります。
令和7年4月21日、新しい提案および方針を追加いたしました。
リユースシステムについて
- 内容
- 家じまいする方がいます。食器などごみステーションに出さなければなりません。必要としている方に無料で提供できるようなシステムをつくることはできないものでしょうか。
- 市の対応・方針
-
当市のごみ減量化対策に関して貴重なご提案をいただき、感謝申し上げます。
ご提案のありましたご家庭で使わなくなった製品を必要とする方に譲る再使用(リユース)は、ごみ減量化対策として市としても推進しております。
現時点では市が独自でリユースシステムを構築する予定はございませんが、民間のリユースシステムが充実しておりますので、リサイクルショップなどの既存システムの有効活用をお願い申し上げます。
今後とも、ごみの減量化に向けて、引き続き理解とご協力をお願い申し上げます。
令和7年4月21日公開
東由利健康増進センターのトレーニングルームの、筋トレ、有酸素運動マシンの講習会やケーブルテレビでの使用方法の紹介
- 内容
- 東由利健康増進センターのトレーニングルームの、筋トレ、有酸素運動マシンの講習会やケーブルテレビでの使用方法の紹介
- 市の対応・方針
-
東由利体育館(東由利健康増進センター)では、トレーニング機器の使い方を各マシン付近に掲示しています。
市の施設ではナイスアリーナや市総合体育館においてトレーナーが常駐してのトレーニングができる状況にあり、この他には利用者の都合に合わせてトレーニングのやり方などを聞くことができる民間のトレーニング施設もございます。
このため、東由利体育館での講習会開催の計画はございませんが、器具の適切な利用にあたっては、利用方法掲示のほか、動画などを活用した周知方法を検討いたします。なお、由利本荘市公共施設等総合管理計画に定めているとおり、将来的にトレーニングジムはナイスアリーナのみとし、ナイスアリーナ以外のジムの更新は行わないことにしております。
令和7年1月28日公開
ごてんまりコーナ(スペース)の設置をお願いいたします
- 内容
-
由利本荘は「ごてんまりの町」として駅のラッピング、バスの名前など、ごてんまりに関連したものがたくさんあります。
その歴史からごてんまり購入まで1カ所で見たり利用できるコーナーがありません。郷土資料館に展示してはいますが、カダーレの中の一部屋くらいのところでコーナ(スペース)を作っていただくことはできないでしょうか?
ごてんまりの昔からの伝統を守りつつアクセサリーなど新しい品をつくる若い方達もいます。
ごてんまりコーナー(スペース)の設置をご検討お願いいたします。
- 市の対応・方針
-
本荘郷土資料館は、市民の皆様や本市を訪れる方々に収集した資料を広く公開し、本市の歴史や文化、祖先が残した生活の様子を紹介するとともに学習できる場を提供することを目的の一つとしており、その中で本荘こけしや本荘刺し子などの地域工芸品とともに本荘ごてんまりコーナーを常設展示していることは、観光においてもPR効果が高いものと認識しております。
また、羽後本荘駅西口前の通り沿いにあるお土産品店などで本荘ごてんまりを購入することができます。
カダーレは、芸術・文化の振興や市民の交流活動を支援する場として日々多くの方に利用されている施設であり、ごてんまりの魅力を紹介するための十分なスペースを常時確保することが難しい状況ですが、制作するのに高い技術と時間を要する大きな本荘ごてんまりを展示し、来場者の皆様にご覧いただいております。
毎年10月には「全国ごてんまりコンクール」を開催しており、全国から150点を超える多彩な作品が出品され、ごてんまりの美しさや華やかさ、巧みな技術などを間近で見られるとともに、ごてんまりの制作体験や実演・販売コーナーも設けられ、短期間ではありますが、ごてんまりの魅力を堪能できる内容となっております。
昨年は、羽後本荘駅の西口階段や壁面に本荘ごてんまりをデザインした装飾や大型タペストリーを設置したほか、駅内にある情報発信施設には本荘ごてんまり使ったフォトスポットを設置し、観光などで駅を利用される方にごてんまりの魅力を発信しております。
今後も、本荘郷土資料館の常設展示を周知するとともにさまざまな形で本荘ごてんまりの魅力を発信し、本市の知名度向上や観光振興に繋げたいと思っておりますので、ご理解のほどをお願い申し上げます。
令和7年1月24日公開
事前投票所の巡回について
- 内容
-
選挙の際、高校生が投票しやすいように各高校を事前投票所バスで巡回して下さることを提案します。
若者の投票率の低迷が課題となっておりますが、18才になってすぐの選挙で投票することが大切だと思います。
しかし高校3年生ともなれば、部活や補習授業等で投票所へ行くことが難しい生徒もたくさんいると思います。
そこで事前投票所のバスを準備し、昼休みや放課後に投票できるよう市内の各高校を巡回していただきたい。
先輩たちが投票する姿を見れば後輩たちも「今度は自分たちが投票するぞ」という気持ちになることと思います。
次回の選挙で実現されることを期待しています。 - 市の対応・方針
-
平成28年より選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、若年層の投票率は依然低い水準にとどまっております。
選挙管理委員会事務局といたしましても、若い世代への投票支援策の重要性を認識し、高校生を対象にした選挙啓発出前講座を行っており、実際の選挙機材を使用した模擬投票を体験してもらうなどの活動を行ってまいりました。
ご提案の件につきましては、これまで県立大学に投票所を設置した実績がありますので、それに加えて、できる限り早期に移動期日前投票所の設置について、市内の高校と協議してまいりたいと考えております。
今後もなお一層、若い世代が選挙に関心を持ってもらえるような啓発活動に努めてまいりますのでよろしくお願いします。
令和7年1月24日公開
路線バスの今後のこと
- 内容
-
バスも乗る人が少なくなりバスの運転手不足も重なって、バスの本数が少なくなってきた。
来年も本数を減らされると移動することもままならないため、1年に1回でもいいのでバス代の半額補助を実施してほしい。
車の運転免許証を返納されたお年寄りも利用しているし、病院に通うにも不便になるのでこれ以上本数を減らされると大変です。 - 市の対応・方針
-
由利本荘市ではこれまで、市内を走るバス路線の赤字に対して補填を行うことで、路線の維持を図ってまいりましたが、ここ数年で路線バス事業者は深刻な運転士不足の状況を抱えることとなり、路線の維持についてはバス事業者と協議を行いながら、皆様の「移動手段」が確保されるよう働きかけている状況です。
市ではさまざまな取り組みを実施しながら、引き続き路線の維持に向けて尽力してまいりますので、これからもご利用いただけると幸いです。
また、ご提案いただきました「路線バスの回数券の半額割引き」につきましては、由利本荘市では現在実施しておりませんが、昨年度までに実施した際、販売継続を求める声も一定数ありましたので、引き続き検討を重ねてまいります。
令和7年1月22日公開
子育てしやすい由利本荘市
- 内容
-
私は由利本荘市で0歳双子を含む子供を育てています。由利本荘市では子育てに関するサークルやイベントが以前に比べて増えて来ましたが、多胎児(双子や三つ子)に関するものは何1つありません。
秋田市でそのようなものは見かけますが、妊娠中や子供を連れて秋田市へ出向くのは厳しいです。そのため、多胎児に関する情報を得られる場や相談できる所が無く、私自身とても不安な妊娠期間だったし、今現在も大変です。
ファミリーサポート事業はあるものの、お願いすると結構なお金がかかるため、なかなか利用したくてもできない現実です。
そして、多胎児家庭に向けた支援も無く、金銭的にも厳しいです。ミルクやオムツ、服、育児グッズなど…沢山の物が必要で児童手当のみでは足りないです。
現在、不妊治療をしている人が増えているため、双子や三つ子は以前より増えていると聞きます。
多胎児家庭に対する支援を充実させてほしいと思います。
- 市の対応・方針
-
健康づくり課では、面談の場で、産前産後の体調や生活をサポートするために、妊婦健診、子育世帯訪問支援事業、産後ケア事業などの説明やご案内をしております。
これらの事業は、多胎を育てるサポートとして、お子さんの人数にあわせて利用回数を増やして対応しております。
妊娠期から子育て期にわたって不安や悩みなどの相談については、本荘保健センター内にございます「ふぁみりあ」において保健師や助産師といった専門職員が相談に応じますので、ぜひご利用ください。
尾崎小学校の隣にあるこどもプラザ「あおぞら」でもスタッフが子育て相談に対応しておりますので、お気軽にご利用ください。
市内に多胎児家庭に特化したサークルはありませんが、ニーズがあることを既存サークルに情報提供し、いただいたご提案を踏まえて、子育て世代のニーズに沿った事業を検討してまいります。
経済的な支援につきましては、児童手当が、令和6年10 月からの制度改正に伴い、対象が高校生年代まで拡大となり、第3子以降は3 万円に増額されています。
児童手当のほか、本市では以下の事業を行っておりますので、子育て費用負担の軽減にお役立てください。
- 出産・子育て支援交付金:妊娠時に5万円、出産時は、こどもの数に応じ、県からの2万円を合わせて7万円が給付。(双子出産の場合には、出産後に14 万円が給付されることになります。)
- 子育て支援金:第2 子以降が対象。第2 子には10 万円、第3 子以降にはこども1人あたり20 万円を支給。
- 子育てファミリー支援事業:ミルク代やおむつ代、ファミリーサポートセンター事業の利用料など未就学児にかかる子育て費用に対し最大15,000 円の助成。(3人以上の子の養育などの要件あり)
令和7年1月22日公開
駅前バス停にベンチを
- 内容
-
羽後本荘駅前からバスを利用する方のため、ベンチを設置して欲しい。
- 市の対応・方針
-
羽後本荘駅については、令和3年8月に駅舎が改築され、駅前広場については令和5年4月に整備が完了しました。
駅舎を改築する際、市では駅構内1階に観光情報発信施設を設置し、市内のイベント等の情報発信を行っております。観光情報発信施設の室内には、バス時間まで待機できるようなスペースもありますので、市内のイベント情報をご覧いただきながら、バスをお待ちいただくことができます。道路側はガラス張りとなっており、バス車両が近づいてくるのが見えるようになっておりますが、バス停からは少し距離がありますので、発車時刻に遅れないようご注意ください。
最後にご提案のベンチの設置についてですが、昨今、夏場の気温は35度を超えることもありますので、できるだけ駅構内をご利用ください。
令和7年1月14日公開
歩道の設置
- 内容
-
グランマート本荘南店から薬師堂駅まで、通勤時間帯はかなりの交通量があるのに、道が狭く歩道がありません。
付近に住んでいる人はもちろん、薬師堂駅から歩いて本荘高校に通う学生が安全に通れるように、道路の拡張や歩道の設置を提案します。
- 市の対応・方針
-
本市では、市道鶴沼薬師堂線道路改良事業として薬師堂踏切からグランマート本荘南店までの約700m区間について歩道も含めた全幅12.5mの道路拡幅を計画しております。
この道路改良事業については令和3年度より開始しており、これまで測量、設計、建物等の補償調査を実施しておりましたが、本年度より用地取得や建物補償を進めているところです。
なお、事業完了には数年の期間を要しますことから、安全な通行にご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年12月27日公開
子どもたちが遊べる施設がほしい
- 内容
- 由利本荘市にも大型室内遊び施設がほしいです。
雨の日や猛暑の日、大雪の日など外で遊ぶのが難しい時にそういった施設があるととても助かります。また、年が離れた兄弟で遊ぶ場合も幼児エリア、児童エリアと分かれていて安全に遊ぶことができ、色んな年齢のこどもを思いっきり遊ばせることが出来るのもとても魅力です。
現在由利本荘市には、木のおもちゃ館とあおぞらが室内で遊ぶ施設となっていますが、木のおもちゃ館はやや遠くお金がかかるという面で頻繁に行くことが出来ず、あおぞらは土日の利用者が多いのに規模が小さく遊びにくいのが難点です。
隣の山形県には、げんキッズやべにっこひろばなど、無料で遊べる大型室内遊び施設が多くあります。宮城県や福島県にも増えています。由利本荘市にもそういった施設が出来ることで、今よりも子育てしやすい環境になると思います。 - 市の対応・方針
- 本市には、屋内で遊べる施設としては、代表的なものとして、こどもプラザ「あおぞら」や木のおもちゃ館などがございますが、今後、新たな施設の整備にあたっては、子育て世代のニーズ、施設の用途及び地域の特性、設置後の維持管理経費や管理運営手法、近隣施設や類似施設の機能複合化や集約化といったさまざまな観点からの分析、更に今後の人口減少を見据えた長期的な検討を踏まえた上で、適切な整備を検討してまいります。
令和6年8月30日公開
由利本荘総合防災公園について
- 内容
-
天気の良い日や土曜日、日曜日などの休日は公園内で小さなお子さんとパパママ、小中高生などが楽しそうに遊んでいます。大声を出しても自由に走り廻っても安心です。見ているこちらも幸せな気分になります。
子供達が自由に遊べる場所が少なくなっていますので、防災公園はとても貴重な場所になっていると思います。
しかし、これから暑い時季の日除けや急な雨対策的意味の屋根付スペースや屋根付ベンチなどあればもっと利用度が高いのではないでしょうか。
防災公園内に屋根個所設置を希望します。
- 市の対応・方針
-
由利本荘総合防災公園の広場は、児童生徒、ご家族連れで遊んでいただける屋外施設として多くのご利用をいただいております。
屋根付きスペース、屋根付きベンチにつきまして、総合防災公園には緩やかな遮光効果をもたせた日よけ設備のあるベンチを設置しており、多数ご利用いただいております。
年々夏の暑さが厳しくなり、屋外での熱中症対策の重要性が増しておりますが、日陰スペースの確保も含め、より魅力的な公園となるよう整備について検討を進めてまいります。
なお、総合防災公園は屋外施設とナイスアリーナが一体となっております。ナイスアリーナは指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定されており、熱中症を予防するためにロビーにて無料で休憩することができます。
屋外活動は十分に気を付けて行う必要がありますが、ナイスアリーナを休憩場所としてご利用の上、楽しく遊んでいただきたいと存じます。
令和6年8月5日公開
若者への娯楽からの街づくり
- 内容
-
今の由利本荘市は飲食店があまり多くないイメージがあります。
大手企業が工場を建て、社宅アパート等の建築も済みその影響もあり由利本荘市には若い年代の人が集まりつつあります。
それなのにその地域周辺には娯楽施設や飲食店が全くなくこれでは定着する前に離れていってしまうのではと思います。
なので、夜間、広い敷地を利用した建築費などもかからず場所も選べるキッチンカーを集めて期間限定で飲み屋街を作って楽しんで貰う、そんなイベントがあると盛り上がるのではないかと思います。
キッチンカーに限らず出店希望のお店をどんどん募って各各知名度を上げてお店に来てもらう。そんなきっかけを作ることもできると思います。
- 市の対応・方針
-
官民連携で進める「一番堰まちづくりプロジェクト」の一環で整備されたTDK社員寮「ZiNOBA(ジノバ)」では、オープニングフェスをはじめ寮で生活する若者だけでなく地域と交流できる催しが開催されており、本市の賑わい創出に寄与する取組が行われております。
ご提案の、期間限定でアルコールを提供できる場を市が主催することは難しいですが、市では「商店・飲食店等イベント実施支援補助金」を設け、商店街や飲食店が自主的に取り組むイベントに対して補助を行っているほか、業種を問わず新たに起業する方へ支援し賑わいづくりに努めております。
いただいたご提案は今後の消費促進イベントや賑わいづくりの参考にさせていただきます。
令和6年8月5日公開
学校に民間の風を入れたい
- 内容
-
他自治体の学校では学校教育だけでなく、町のいろいろな仕事をしている一般の人を招き、講演やお話会をしているところもあると聞きました。
子供達が今後、自分の進路を決めたり、さまざまな職を知って多様性のある考え方をするために、今、町で働いている人に教育現場に入ってもらい「働く人の声」、生の声を届けるような機会が由利本荘市でも増えたらすてきだな!と感じました。
子供達の視野が広がるような(職場体験だけでなく)場を今すぐでなくとも作ってほしいなと思いました。
- 市の対応・方針
-
本市では、全小・中学校においてコミュニティ・スクールを導入しており、学校、保護者、地域、行政等が連携を図りながら、各地域の特色を生かした教育活動に取り組んでおります。
その中で、さまざまな取り組みをとおして幅広い世代の人々と触れ合う機会が設けられています。
例えば、学校でキャリア講演会を企画し、卒業生や地域の方から仕事や生き方についてお話ししていただいたり、授業に農業関係者等の専門家をお招きして、体験活動を行ったり、お話を聞いたりしております。
また、このような取り組み以外にも、農業団体と連携し、小学生が搾乳等をとおして酪農について学ぶ体験活動を行ったり、市と県が共同で「中学生と管内企業のふれあいPR事業」を開催し、中学生が地元企業から仕事内容や魅力についての話を直接聞く機会を提供しております。
各校において、地域の人材等を活用しながら児童生徒の発達段階に応じた学習内容や体験活動に取り組んでおり、今後も、さまざまな人々と関わる中で、考えが深まったり、物事の見方を広げたりする体験や学習プログラムを実施できるよう進めてまいります。
令和6年7月23日公開
犬と人が楽しく過ごせる町 ー地域活性を目指してー
- 内容
-
- 旧前郷小学校跡地(滝沢舘公園)にドッグランを作っていただきたい。
- 近くの空家をリフォームして遠方から来た人が犬同伴で宿泊できる施設(家)を作り、1日~1カ月単位で借りられるようにしてみてはどうか。
- 市の対応・方針
-
ドッグランは、飼い主とペットのコミュニケーションのほか、ペットの適度な運動やストレス解消など多くのメリットがあると認識しております。
本市においてもペットショップやペット霊園に併設されたドッグランがあるほか、令和5年度には本市の地域おこし協力隊により、簡易ドッグランの設置と
キャンプを兼ねたイベントが実施されるなど、少しずつではありますが広がりをみせております。
しかしながら、滝沢舘公園へのドッグラン開設につきましては、費用対効果や運営面の観点から公設での設置は難しいと考えておりますのでご理解願います。
なお、公園内の遊歩道を利用してペットとともに散歩している方もお見かけしますので、ドッグランはございませんが、今後も公園をご利用の上、地元の住民の皆さまと交流を深めていただければ幸いです。
空き家は個人の資産であるため、市が空き家をリフォームすることや宿泊施設等として利活用することについては、現在のところ考えておりません。
なお、「お試し移住体験施設」のペット同伴利用につきましては、今後の利用希望者の動向を踏まえながら、必要に応じて検討してまいります。
令和6年7月23日公開
野良猫対策について
- 内容
-
新聞報道でにかほ市の猫の不妊去勢手術費補助金制度の拡充を知りました。
私の町内にも野良猫が住みついております。
自分もペットを飼っており、猫も嫌いではないのですが、年に何度も出産を繰り返し繁殖している状態です。
望まれない繁殖で、家猫であれば、今は20年近くも長生きする時代に、野良猫というだけで長生きできなかったり、病気に感染したり、食べる事や暑さ寒さをしのぐのにも野良猫なりに苦労をしていると思います。
同時に、私たち近隣住人も野良猫のふん尿被害に悩まされております。
行政や秋田市のわんにゃんピアにも相談しましたが、野良猫は捕獲することができない事を知りました。
対策としては、住みついているお宅で餌付けをしない。あとは、繁殖しないように不妊去勢手術をする。
ただ、費用が掛かる事なので簡単なことではありません。猫の為にも人間の為にも何か良い方法はないのか考えさせられます。
今回のにかほ市の制度を知り、由利本荘市でも是非、このような対策に取り組んで欲しいと思います。 - 市の対応・方針
-
飼い主のいない猫や多頭飼育猫への市の対策につきましては、市民のみなさまから寄せられた情報などをもとに、状況の確認や飼育方法の調査などを行い、保健所など関係機関と連携しながら、適正飼育へのアドバイスとして、里親制度の説明や、不妊手術助成金事業を行っている団体を紹介する体制をとっております。
また、令和5年度より県が新たに支援を開始した、地域のみなさまがその地域に住む飼い主のいない猫を管理する「地域猫活動」について、市としてもその制度を紹介するとともに、活用状況や効果などを注視しているところであります。
市といたしましては、現時点で補助金制度の新設は予定しておりませんが、今後も広報や市ホームページ、地域へのチラシ配布等により適正な飼育を呼びかけるほか、市民のみなさまからの苦情・相談への丁寧な対応を行いながら、頂いたご意見も参考にするなどし、問題解決に努めてまいります。
令和6年7月19日公開
若者世代に希望を
- 内容
-
由利本荘市では若者、子育て世代が苦境に立たされていると思います。
18歳で高校を卒業したら働く場所が少ない、もしくは、あったとしても低賃金で将来を考えられず由利本荘市外、県外を選ぶ人が多数。
そして、本人の頑張り、または運が良く働く場所が決まったとしても、今度は若者が少なく、結婚ができない。
運良く相手と出会い、結婚出来たとしても子育てできるほど余裕がなく、子供を諦める世帯もあるのが実情です。
この状態で希望あふれるなんてゆるい言葉を言われても正直危機感がないのではないのかなと思ってしまいます。
提案として徹底的な若者への支援、援助。
具体的に減税、補助金、出会いの場作り、広報、大企業優遇、誘致。 - 市の対応・方針
-
市では、創業時の固定資産税の課税免除や雇用奨励金交付などの支援制度を設け、企業訪問や立地セミナーでのPR活動を通して、大企業も含め魅力ある企業の誘致に取り組んでおります。
今後は、洋上風力発電事業をはじめとしたメガインフラ事業により、施設のメンテナンスなど新たな仕事の増加も見込まれており、そのような分野へ進出する地元企業への支援も行っています。
多様な産業の誘致に加え「起業するなら由利本荘で」を目指し、若者や女性が起業にチャレンジしやすい環境の整備にも力を入れており、多様な働き方の促進と新たな産業や就業機会創出のため取り組みを進めてまいります。
また、官民連携で取り組んでいる「一番堰まちづくりプロジェクト」において、電子部品大手のTDK社員寮が完成し、多くの若者が居住をはじめています。
今後も商業施設や事務所の建設が計画されており、事業者や住民の皆様と一体となって取り組む新たなまちづくりが人を惹きつけ、賑わいを生み出し、地域活性化とともに若者の定住促進につながるものと大いに期待しているところです。
出会いの場をつくる取り組みとして、スポーツや体験型イベントを通して若者の交流を促進する「アベイバ(あんべいい場所)プロジェクト」により、若者の自然な出会いの場を創出しております。
また、スマホからのお相手検索やAIマッチング機能を備える「あきた結婚支援センター」への入会を推奨し、初回の入会登録料を助成しており、アナログとデジタルの両面から出会いの場づくりを支援しております。
市の取り組みについて、若い世代や子育て世代に広く認知してもらえるよう、SNSなどの媒体を活用した情報発信に努めてまいります。
令和6年7月19日公開
Instagram等のSNSの利用状況の悪作
- 内容
-
由利本荘市は県内でもデジタル化に対して早く行動されている市というのは、凄く好感が持てるところではあります。
しかし、SNSが無料広告、宣伝媒体としてどこの市町村も力を入れてる中で、寂しすぎるフォロワー数、いいね数。YouTubeに至っては3桁程度の再生数。
全てに共通しているのは、お役所仕事の片手間感と、媒体のニーズに合わない投稿が多い。という事にあると思います。
YouTubeなのに、観光案内所みたいな内容ばかりだったり、定期投稿が出来てなかったり。
インスタグラムも、キラーコンテンツも無くストーリーとポストの棲み分けもなく、ただただリポストだったり、ポスター読めばわかるような事の再掲載。
たぶん普段の業務が忙しく、SNSまで手が回らないのかな?と思っております。
そこで、市内には個人で活動しているインスタグラマー、ティックトッカー、ユーチューバーなどのSNSに特化した方々はいます。その方々に委託したり、そういう人達の力を借りて、寂しいSNSを盛り上げてみてはいかがでしょうか?
YouTube、TikTok、Instagram、どの媒体にも特徴がありそれを外すと誰もみない物です。
そこを抑えている市民の専門家に頼る事が大事なんだと思いますし、市民参加型のSNSは数字も注目度も上がると思います。 - 市の対応・方針
-
本市ではX、Facebook、LINE公式アカウントおよびYouTube(ゆりほんテレビ)を運用しております。
Instagramは移住支援課(アカウント名:yurihonjocity_iju)、まるごと売り込み課(アカウント名:yurihonjocity_urikomi)が運用しており、それぞれ定時投稿やハッシュタグの活用など、ニーズに合わせた情報発信となるよう研究を重ねながら運用しているところです。
ご提案の外部委託に関しては、費用対効果の他、SNSが災害時の情報伝達手段の一つともなることから、慎重な検討が必要と考えております。
引き続き広報広聴課(情報発信担当)が中心となり、SNSによる効果的な発信方法の研究を続けてまいります。
令和6年7月19日公開
保育料を無料に
- 内容
-
子どもが今年から保育園に行くようになりました。正直、保育料の高さにびっくりしています。同じサービスを受けているのに収入によって違うのも疑問に思うところです。
出来るのであれば無料にして欲しいと言うのが本音です。
私は、子どもは市の宝だと思います。なかなか財政としても厳しいとは思いますが、秋田県に住みたいって思ってる人が保育園が無料という事をきっかけにでも、由利本荘を選んでもらえたらと思っています。
子育てをしやすいというのは居住する上で優先度はかなり高いポイントだと思います。
他の市との明確な違いをアピール出来れば10年後、20年後の由利本荘市に繋がると思っています。どうか大好きな由利本荘市この先のためによろしくお願いします。
- 市の対応・方針
-
認可保育施設の保育料は、世帯収入から算出される「市町村民税所得割課税額」に応じて、国の定める水準を限度として、実施主体である市町村が定めることとされております。
3歳児から5歳児については国の制度により保育料が無料となりますが、3歳未満児の保育料については、世帯収入によって区分けされた階層により保育料が設定されております。
本市では、国基準の保育料を約4割軽減し、加えて「すこやか子育て支援事業」により、保育料及び3歳以上児の副食費を助成するなど、子育て世帯の負担の軽減に努めているところです。
3歳未満児の保育料無償化に関しましても、市の財政状況等を踏まえながら検討を続けているところですが、今後とも子育て支援策の充実に努め、安心して子育て出来る社会の形成に取り組んでまいりますのでよろしくお願いします。
令和6年7月1日公開
市営住宅等の入居者の収入上限金額について
- 内容
-
市営住宅等の公営住宅の入居者の収入には上限が設けられており、それを越える収入があった場合は家賃が割り増しになったりします。
ですが、物価高、円安、異常気象等によりほぼ全てのものが値上がりし、光熱費も値上がりしています。
それを補おうと収入を増やす努力をすれば、増えた額よりも家賃の割り増し額が大きくなったり、何より退去しなければいけなくなって住む場所を失うおそれがあります。
どうか収入の上限を上げてください。
- 市の対応・方針
-
公営住宅の入居資格者資格である収入月額は、公営住宅法により「15万8千円以下で事業主体が条例で定める額」とされております。
これに基づき、由利本荘市では由利本荘市営住宅管理条例の中で、収入月額を15万8千円以下と定めており、国で定めた金額を基準としております。
また、家賃は入居者の収入に応じた金額となっており、その収入区分は公営住宅法施行令により定められています。
以上により、市独自に収入月額の基準を引き上げることや、家賃算定の基礎となる収入区分を変更することは、現行法では不可能となっております。
何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
令和6年7月1日公開
菖蒲公園の移設
- 内容
-
近年、菖蒲カーニバルや菖蒲音頭など市民に定着してきていますが、市の花である菖蒲を観賞出来る菖蒲公園が塩害のせいなのかさっぱり咲いていないように思います。
この際菖蒲公園を本荘公園の下の追手門の所の広場に移設してみてはいかがでしょうか?
隣の横手市では浅舞公園で毎年あやめまつりを開催し大変賑わっています。
もちろん本荘公園の上の方にも菖蒲が観れる処を整備する必要も出てくるかもしれませんが、現状あそこの公園下の広場は殆ど活用されていないように思います。
出初式は尾崎小学校のグランドを使うようにすれば良いと思います。課題としては駐車場が少ない事が考えられます。
移設が難しいとしてもあの広場一面に菖蒲があれば人は観に来ると思います。
- 市の対応・方針
-
旧本荘市時代の市の花の名がついている菖蒲公園ですが、近年育成状況が芳しくなかったことから、令和元年度には土壌改良を行うとともに品種や植える間隔等配慮し、苗の植え替えを実施しました。
その結果、令和3年度には育成改善が見られたところですが、翌年度以降の開花状況は芳しくない状況です。菖蒲田周辺の環境が以前と変化していることも一因と考えられ、環境の変化も研究しながら開花状況の改善が図られるよう維持管理に努めているところであることから、公園の移設などは考えておりません。
なお、本荘公園は城址公園として整備され、観桜会や菖蒲カーニバルなどのイベントに活用されているほか、ウォーキング、親子や子供の遊び場など多種多様な目的で、多数のご利用をいただいております。
一方、菖蒲公園は菖蒲の名勝として親しまれ、花などの観賞や散策を目的に開設された公園であります。
市内には他にもさまざまな公園がありますので、利用者の目的に応じて各公園をご利用いただきたく、ご提案いただきました本荘公園への菖蒲の植栽の実施は、現在考えておりませんのでご理解をお願いいたします。
なお、現在、広場での出初式は実施しておりませんので補足し回答いたします。
令和6年7月1日公開
続 本荘IC付近の渋滞について
- 内容
-
以前よりの本荘ICの渋滞について。
ファミリーマート付近の南内越方向への進行の右折時差式信号なのですが、時差式信号がわかりづらい為と三条方向に進行するクルマが多い事により、南内越方向右折渋滞と右折事故が発生している。時差式信号はありがたいが、さらなる安全と渋滞緩和の為に、時差式右折信号を右折矢印信号に変更してもらいたい。
- 市の対応・方針
-
信号機を管理する県公安員会からは「二十六木交差点は、丁字路交差点であり、時差式が最も適している」との意見がありますので、現状の運用となります。
今後開催される「本荘工業団地周辺渋滞対策検討会」においてご意見があった旨、報告させていただきます。
令和6年7月1日公開
バス通学希望者へのバス代補助制度の導入・スクールバスの導入
- 内容
-
先日、通学路に熊が出たため、送迎してほしいという連絡が学校からきました。これはいつまでつづくのでしょうか。
昨年の熊の冬眠前の送迎は約2カ月続きました。歩けないのに通学路と言えるのでしょうか。
春は熊の出没、夏は朝から熱中症アラート、秋もまた熊の出没。
子どもたちの安全を守るための仕方ない事とはいえ、 夫婦共働き、核家族が増えてきている中での負担はとても大きいです。
このような状況下でお願いしたい事があります。
具体的にはバス通学希望者へのバス代補助制度の導入、もしくはスクールバスの導入の検討です。
前々から、子どもが歩いて行くとなると、1時間近くかかる片道約3kmの距離なのにも関わらず、補助が何を出ない事に対して疑問を抱いていました。
あの道は大人ですら歩くのは大変です。にかほ市はこれぐらいの距離だとスクールバスで通学しているという話も聞いています。
この機会に今一度検討をお願いしたいです。
きっとこのような考えを持っている親は私だけではないはずです。
今の子どもたちがこれからも住み続けたいと思えるような街づくりに期待しております。
今後とも子どもたちの健やかな成長と安全を共に守っていけるようご協力をお願い申し上げます。 - 市の対応・方針
-
スクールバスの運行についてですが、国からの指針では遠距離通学は小学校で4km以上、中学校で6km以上とされており、この基準に沿ってバスを導入し運行しています。
また、この指針を満たしていても公共交通機関を利用できる場合は、スクールバス利用ではなく、路線バスや電車を利用していただいており、その定期代を補助しております。
遠距離通学に関する市からの助成につきましては、国からの補助金や交付金を受けて、国の指針に基づく、市全域で統一した基準により実施しております。
また、生徒がどのような方法で通学するかについては各学校の判断となります。支援の対象とはなりませんが、徒歩以外の通学方法が認められることもありますので、学校へ一度ご相談くださいますようお願いいたします。
目撃が続発している熊への対応につきましては、学校への送迎をお願いされている保護者の皆さまには大変負担をおかけしております。学校からも協力をいただき、目撃件数が多い朝の通学時に職員や地域の方の見守りを実施しておりますが、今後も関係機関と連携し熊出没の情報を把握し、生徒が安全に通学できるよう見守りや、他の有効な対策などについて検討をしながら対応していきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和6年5月20日公開
通学路の安全確保
- 内容
-
西目ローソン前の横断歩道と新道下踏切に街頭指導で立ちました。
朝の通勤ラッシュと重なり、子供たちは白線ライン内を歩いていますが、特に踏切ではランドセルと車がすれすれにすれ違う状況です。
子供達が車が通り過ぎるのを踏切上で待っている状況ですので、踏切の歩道の設置を提案します。
近隣に中学校前の横断歩道、高校前の横断歩道はありますが、ちょうど中間地点に住んでいる子供たちは通学に便利な経路になります。
子供たちの安全のために再度ご検討よろしくお願いします。
- 市の対応・方針
-
本提案箇所につきましては、現在のところ、歩道設置などの道路改良の計画はございません。
また、踏切内の拡幅には多額の事業費がかかるため、早期の実現は困難であります。
市といたしましては、児童・生徒の安全を確保するため、通学路合同点検の際に関係諸機関と協議いたします。
令和6年5月13日公開
熊出没多発地区における通学4km以下地区へのスクールバス運行継続を検討下さい
- 内容
-
毎年のように東由利小学校では熊の出没への対策として4km以下の地域での春から秋にかけてのスクールバスの運行継続が要望されております。
文部科学省の公表するスクールバスの運行の資料では、4km以下の地域であっても有料で運行する地域や自治体等の財源でカバーすることで無償で運行している事例が公表されており、直近では、羽後町にて熊の出没がみられた地域において冬季から引き続きスクールバスを運行することが報道されております。
東由利地域における人的資源・財源に限りがあることは周知の状況ですが、矢島同様に小学校・中学の統合を進めることで共通コストを減らすなどすれば、スクールバスの運行財源の捻出も可能ではないでしょうか?
遠くない将来、当地域はスクールバスの運転手確保にすら事欠く未来が予想されますが、本荘地域へのバス運行による通学は現状では通学時間からして不可能です。
15年先までは少なくとも子供がいますので、長期的な視野に立って安定的な雇用としてのバス運転手の確保できる体制をご検討頂ければ幸いです。 - 市の対応・方針
-
ご要望のありましたスクールバスの運行についてですが、国からの指針では遠距離通学は小学校で4km以上、中学校で6km以上とされており、この基準に沿ってバスを導入し運行しています。
また、この指針を満たしていても公共交通機関を利用できる場合は、スクールバス利用ではなく、路線バスや電車を利用していただいており、その定期代を補助しております。
スクールバスの利用につきましては、国からの補助金や交付金を受けて、国の指針に基づき、市全地域で統一した基準により実施しており、残念ながら基準を満たさない児童・生徒は対象となっておりません。
また、児童・生徒がどのような方法で通学するかについては各学校の判断となります。支援の対象とはなりませんが、徒歩以外の通学方法が認められることもありますので、各学校へ一度ご相談くださいますようお願いいたします。
市全域で目撃が続発している熊への対応につきましては、目撃件数が多い朝の通学時に、職員や地域の方の見守りを実施しております。
今後も、関係機関と連携し熊出没の情報を把握しながら、児童・生徒が安全に通学できるよう見守りなどの対策を実施してまいります。
ご意見にもありましたように、通学を含め交通を維持するために必要な人材の確保については、本市の喫緊の課題であります。
地域ごとに交通事情が異なりますので、地域の皆様のご意見を伺い、関係機関と協議し対策をすすめていきたいと存じます。
令和6年5月10日公開
このページに関するお問い合わせ
企画振興部広報広聴課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6237 ファクス:0184-24-6090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。