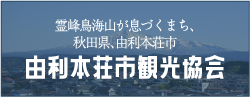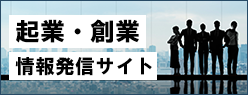令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
重要なお知らせ
申請内容に不備があり不備通知が送付されている方については、令和7年10月14日火曜日を最終的な返送期限としております。
支給対象となる方が期限までに申請等の提出をされない場合、給付を辞退したものとみなされます。
給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください
市町村や都道府県、国等から、以下のようなことを求めることはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること
- 電子申請をしていないのに市からメールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること
その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
給付金に関するお問い合わせ先
定額減税補足給付金に関するお問い合わせは物価高騰対策給付金事務局にて対応いたします。
由利本荘市物価高騰対策給付金事務局
市では、この給付金に関するお問い合わせ業務を委託しています。事務局の所在地は、大仙市となります。
対応期間は令和8年2月28日まで(土日祝日含む)、対応時間は午前8時30分から午後8時までです。
不足額給付について
以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する場合に給付されます。
この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年12月28日公布)の規定により受給権の譲渡及び差押等が禁止されています。
また、同規定により非課税所得となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)所要額が、確定した令和6年分所得により算出した定額減税補足給付金(不足額給付)所要額よりも低かった場合、その不足額を給付するものです。
なお、給付金額を算出するための税情報の基準日は令和7年6月2日時点のものを使用し、以後の修正申告等による変動は加味されません。
不足額給付1の給付額
給付額=定額減税補足給付(不足額給付)所要額(1万円単位に切り上げ)-令和6年度定額減税補足給付(調整給付または当初調整給付)所要額(自治体より決定された額)
- 定額減税補足給付(不足額給付)所要額
=令和6年分所得税控除不足額(A)+令和6年度住民税控除不足額(B)
ただし、令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割額がどちらも非課税(定額減税前)の場合はゼロ
定額減税控除不足額
- 令和6年分所得税控除不足額(A)
=所得税定額減税可能額-令和6年分所得税額(令和6年中の所得を基礎とするもの)
ただし、マイナスの場合はゼロ - 令和6年度住民税控除不足額(B)
=住民税定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(令和5年中の所得を基礎とするもの)
ただし、マイナスの場合はゼロ
定額減税可能額
- 所得税定額減税可能額
=3万円×(扶養親族等数(令和6年12月31日時点)+1)
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合はゼロ - 住民税定額減税可能額
=1万円×(扶養親族等数(令和5年12月31日時点)+1)
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合はゼロ
注:扶養親族等数には同一生計配偶者を含みます。また、国外居住者は除きます。
不足額給付2
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円(定額減税前)で調整給付の対象にならなかった方、かつ、令和5年度もしくは令和6年度の非課税世帯(又は均等割のみ課税世帯)向け給付(他自治体が実施した同様の給付を含む)の対象世帯主又は世帯員に該当していない方であって、以下のいずれかに該当する方。
- 青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円超である方
なお、要件を判定するための税情報の基準日は令和7年6月2日時点のものを使用し、以後の修正申告等による変動は加味されません。
不足額給付2の判定に関する非課税世帯(又は均等割のみ課税世帯)向け給付とは
令和5年度実施
- 追加給付(非課税世帯向け・7万円給付)
- 拡大給付(均等割のみ課税世帯向け・10万円給付)
令和6年度実施
- 新規給付(新たに非課税及び均等割のみ課税世帯となった世帯向け・10万円給付)
他自治体が実施した別名の給付のうち、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の指定枠を活用し実施された同様の給付も含まれますのでご注意ください。
不足額給付2の給付額
原則として4万円
ただし、以下のいずれかに該当する場合はそれぞれに定める額を減ずる
- 令和6年度住民税において、令和6年1月1日時点では国外居住者であった場合や未申告の場合など、令和6年度住民税が課税できない事情があった場合
または事業主の所得が1,805万円を超過している場合の事業専従者または所得が48万円以下で扶養控除対象になり得る場合 1万円 - 令和6年分所得税において、事業主の所得が1,805万円を超過している場合の事業専従者または所得が48万円以下で扶養控除対象になり得る場合 3万円
対象者・申請方法について
対象者
住民税の賦課期日(令和7年1月1日)時点で本市に住民登録がある方、または生活の本拠があり令和7年度住民税の納税義務者となっている方のうち、上記の不足額給付額が発生する方が対象です。
また、令和7年1月2日以降に本市に転入された方(由利本荘市が令和7年度住民税を課税する方は除く)については、不足額給付は令和7年1月1日時点で居住していた自治体での取扱いとなりますので、そちらにお問い合わせください。
申請方法
対象と見込まれる方には市より「お知らせ」または「ご案内」が送付されます。
「お知らせ」が送付された方
市が活動口座を把握している不足額給付1の対象者の方には、「令和7年度由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」を発送します。
「お知らせ」が送られた場合はお手続きは必要ありません(辞退する場合または振込先を変更する場合を除く)。
辞退する場合または振込先を変更する場合は、お問い合わせ先としている事務局フリーダイヤル(0120-553-522)までご連絡ください。
振込先変更の場合は市より変更申請用紙をお送りします。通常の書面申請と同等の処理期間を要します。
「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するご案内」が送付された方
市が活動口座を把握していない不足額給付1の対象者の方には、「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するご案内」を発送します。
「ご案内」が送られた場合は申請が必要です。
申請はご案内に記載の通知IDによる電子申請(最も早い方法)または同封の「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付)支給申請書」による書面申請によります。
「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付2)に関するご案内」が送付された方
不足額給付2の対象者の方には、「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付2)に関するご案内」を発送します。
不足額給付2については、他の自治体で国の「物価高騰対応重点支援地方創生交付金」の指定枠を活用した同種の給付を受給している場合対象外となりますので、そうした事実のない方のみご申請ください。
申請はご案内に記載の通知IDによる電子申請(最も早い方法)または同封の「由利本荘市定額減税補足給付金(不足額給付)支給申請書」による書面申請によります。
令和6年中に由利本荘市に転入され、令和7年1月1日時点で由利本荘市に住所がある方(令和7年度住民税が由利本荘市より課税されている方を含む)
令和6年度の調整給付の詳細および住民税課税状況等が不明のため、不足額給付の判定ができません。
不足額給付1および不足額給付2の給付要件に該当すると思われる方は、お問い合わせ先としている事務局フリーダイヤル(0120-553-522)までご連絡ください。
詳細を確認させていただき、対象となる場合は市より「ご案内」をお送りいたします。
書面申請提出先
書面申請の場合、給付まで1週間から2週間ほど長くかかります。
| 受付期間 | 受付時間 | |
|---|---|---|
| 福祉支援課(鶴舞会館1階) | 令和7年8月18日から9月30日 | 午前8時30分から午後5時まで |
| 各総合支所市民サービス課 | 令和7年8月18日から9月30日 | 午前8時30分から午後5時まで |
| 移動市役所の窓口 | 訪問予定・予約はホームページでご確認ください |
このページに関するお問い合わせ
由利本荘市物価高騰対策給付金事務局
秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール2階エスプール
運用期間 令和7年2月1日(土曜日)~令和8年3月15日(日曜日)
電話:0120-553-522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。