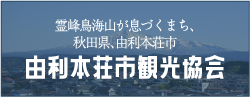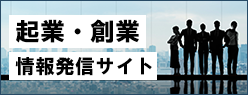介護保険料とその納め方
算定方法
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まります。その基準額をもとに、所得に応じた保険料が決められます。
第1号被保険者の基準額はこのように決まります
基準額(月額)=市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷市区町村の第1号被保険者数÷12カ月
注:市区町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
所得段階別保険料
| 段階 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 |
生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9000円以下の人 |
0.285 | 23,256円 | 1,938円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9,000円超120万円以下の人 |
0.485 | 39,576円 |
3,298円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
0.685 | 55,896円 |
4,658円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9,000円以下の人 | 0.90 | 73,440円 |
6,120円 |
|
第5段階 (基準) |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 1.00 | 81,600円 | 6,800円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
1.20 | 97,920円 | 8,160円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.30 | 106,080円 | 8,840円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.50 | 122,400円 | 10,200円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.70 | 138,720円 | 11,560円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.90 | 155,040円 | 12,920円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.10 | 171,360円 | 14,280円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.30 | 187,680円 | 15,640円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.40 | 195,840円 | 16,320円 |
保険料の納め方
介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
保険料の納め方は2種類に分かれます。
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
| 種類 | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金 | 納め方 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 年額18万円未満 |
納付書や口座振替で期日までに金融機関などを通じて保険料を納めていただきます |
| 特別徴収 | 年額18万円以上 |
年金から天引き (年金から保険料があらかじめ差し引かれます) |
ただし、年金が年額18万円以上でも以下の場合は特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めていただく場合があります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった
- 年度途中で年金【老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金】の受給が始まった
- 他の市区町村から転入した
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった
- 年金が一時差し止めになった ・・・など
保険料の減免
【家屋に被害を受けた場合】
被保険者(申請者)宅の家屋などに被害があった場合、介護保険料や施設等利用料が減免になることがあります。
- 保険料徴収猶予⇒2割以上罹災によって、最大6カ月の徴収猶予
- 保険料減免⇒3割以上罹災によって、30%~100%減免(年度内の未達納期分)
- 利用料減免⇒3割以上罹災によって10%負担の施設利用料が、最大6カ月間3割~10割減免(7%~0%負担)
- 建物共済からの支給「なし」…罹災証明により判定
- 建物共済からの支給「あり」…被害想定額から建物共済支給額を差し引いた額で罹災割合を計算して判定。20%を越えない場合は猶予・減免対象外
【例】
家屋評価額500万円で被害推定額が120万円であり、建物共済からの支給額が100万円の場合は、罹災割合は4%となり非該当となる。
被害想定額(120万円)-建物共済(100万円)=20万円
注:罹災額20万円は家屋評価額(500万円)の4%にあたる。
【主な世帯生計維持者の収入(農業収入含)が減少した場合】
世帯の生計を主として維持する方の収入(農業収入含)が自然災害によって減少した場合の介護保険料・施設利用料等が減免となる場合があります。
介護保険料
徴収猶予…前年比2割以上の減収によって、最大6カ月の徴収猶予
減免…前年比3割以上減収によって、20%~100%減免
施設利用料
利用料減免…前年比1/3の減収によって10%負担の施設利用料が、最大6カ月間、3割~10割減免(7%~0%負担)
【例】
前年収入額が500万円、R6販売収入見込額が300万円、農業共済からの支給額が150万円の場合は、減収割合は-50万円(10%)となり非該当となる。
(R6販売額収入見込額(300万円)+共済収入額(150万円))-前年度収入額(500万円)=-50万円
注:農業共済は雑収入に分類され所得計算の対象となります。
減免申請を受けるために必要となる書類
- 所得証明書(同一世帯の方全ての所得が分かるもの)
- 罹災証明書
- 災害保険金受領書
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
| 国民健康保険に加入している人 | 職場の医療保険に加入している人 | |
|---|---|---|
| 決め方 | 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 | 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
| 納め方 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 |
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。 |
保険料を納めなかった場合
保険料を滞納すると
サービスを利用した際の利用者負担額は、通常はかかった費用の1割~3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
1年6カ月以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることもあります。
2年以上滞納すると
サービスを利用するときに利用者負担が引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費が受けられなくなったりします。
保険料の還付
転出や死亡等によって、介護保険料の再計算が行われ、納めすぎの金額が発生した場合は、還付金としてご本人または相続人の方等にお返しします。
対象者には資格喪失後、約1カ月程度経ってから「介護保険料 過誤納金還付通知書」を郵送します。
還付通知書には、お手続きに必要な書類を同封しておりますので、必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
還付金は、「還付振込依頼書」をもとにご指定の口座へ振込みします。また、月末までに到着したものを翌月26日(休業日は前営業日)に振込みします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。