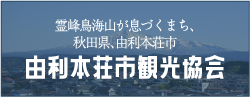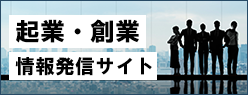食品ロスによる廃棄量について
国内の年間の廃棄量
令和4年度の国内の食品ロスによる廃棄量は472万トンとなっており、令和3年度より約51万トン減量していることがわかります。
また、事業系が約43万トンの減量、家庭系では約8万トンの減量となっております。
-
日本の食品ロス発生量の推移(外部リンク)

環境省より引用しております。
食品ロス発生量の推移を更新しました。(令和4年度)
| 各年度 | 合計数量 | 事業系 | 家庭系 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 472万トン | 236万トン | 236万トン |
|
令和3年度 |
523万トン | 279万トン |
244万トン |
| 令和2年度 |
522万トン |
275万トン |
247万トン |
| 令和元年度(平成31年度) | 570万トン | 309万トン |
261万トン |
注:端末処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。
家庭で捨てられやすい食品
|
順位 |
家庭で捨てられやすい食品 |
捨ててしまう理由 |
|---|---|---|
|
1位 |
主食(ごはん、パン、麺類) |
食べきれなかった |
|
2位 |
野菜 |
傷ませてしまった |
|
3位 |
おかず類 |
消費・賞味期限が切れていた |
食品ロス削減に向けて
消費者にできること
食品ロスは1人1人が食品ロス削減の意識を持ち、実施する事が大切です。
以下の事について意識、実施していきましょう。
買い物の際
1.買い物前に事前に冷蔵庫や食品収納などを確認しましょう。(同じ食品購入を予防できます)
2.必要な物だけ購入する。(安売りで衝動買いは食品ロスにつながりかねません)
3.すぐ使う食品は商品棚の手前から取るようにしましょう。【通称:てまえどり】(お店の売れ残り削減に繋がります)
調理の際
1.食品の特徴を知って無駄なく使用する。(例:ニンジンなどは皮をしっかり洗えば食べられる)
2.自身の予定を把握して作りすぎない。(翌日外食等の予定の場合は前日は食べきれる量を作る)
3.残った料理はリメイクする。(例:肉じゃがの残りはカレー)
食事の際
1.食べられる量を盛るようにしましょう。
2.外食の際は食べきれる量を注文しましょう。(残った場合は自己責任の範囲で持ち帰りましょう)
3.最近では小盛りやハーフサイズの設定をしている飲食店での活用。
-
食品ロス削減ガイドブック(外部リンク)

消費者庁より引用
事業者にできること
小売店
1.規格外や未利用品などの農林水産物の有効活用
2.季節商品(恵方巻など)は予約販売などをこころがける
3.売れ残りしそうな食品は早めの値引きやポイント付与等による売り切り
飲食店の場合
1.通常メニューから小盛メニューへの対応
2.食べ残しの持ち帰り対応(容器設置など)
3.食べ残し啓発ポスター等の掲示
このページに関するお問い合わせ
市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。