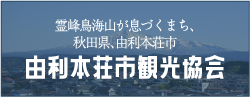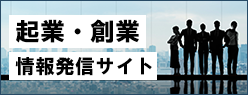整備計画・安全対策に対するご意見等
これまでお寄せいただいたご意見・ご質問をご紹介します。
また、今後いただいたご意見につきましても随時追加してまいります。
HP上でいただいたご意見等(令和7年9月時点)
| ご意見・ご質問 | 回答 |
|---|---|
| 具体的な完成図はいつになったら見れるのか。すぐに出せないなら明確な日付を指定してほしい。 | 施設整備のページに「市民交流学習センター改修工事平面図」を掲載しました。 外構等の整備については準備が整い次第掲載する予定です。 |
| 現在提示されている整備案では、学童整備に関係の無い部分まで学童整備補助金を使って工事するのではないかと誤解しそうになる。 「学童として(補助金を使って)改修する箇所」と「(補助金を使わないが)同時に改修工事を行う箇所」は区別して表示するべきではないか。 |
HP掲載図面を変更いたしました。 |
| 新しい道路によって周辺の危険度が増した印象が強いが、具体的な安全対策を示してほしい。 | ハード面としては、セブンイレブン由利本荘蓼沼店付近の交差点にガードパイプの設置を検討しております。 |
| 信号はいつどこに新設される(あるいは変更される)のか。申請を行った場所と内容、設置時期を明確にしてほしい。 | 信号機は、周辺5箇所において設置等要望を行っております。 以下、要望内容と現在の状況です。 (1)国道108号線から市道薬師堂25号線(R8年度開通予定)との交差地点 ⇒R7年度内での対応は見送られたため、引き続き早期設置を要望してまいります。 (2)本荘東小学校、本荘東中学校の交差点付近 ⇒R7年度中に設置見込みです。 (3)ナイス付近の信号機を押しボタン式から時差式への変更 ⇒R7年度内での対応は見送られたため、引き続き早期変更を要望してまいります。 (4)市道鶴沼薬師堂線、薬師堂踏切付近への横断歩道の設置 ⇒R8~R9市道鶴沼薬師堂線道路改良事業で横断歩道設置予定です。 (5)国道107号線「市民交流学習センター」前の横断歩道への「押しボタン式信号機」設置 ⇒周辺の交通量調査が行われていますが、設置については、引き続き周辺の交通状況等の検証が行われることになります。 |
| 行政センター前の信号設置は他信号との距離の制限があるため、不可能でるときいたが対策はあるのか? 出入りに関して混雑の問題がないということであれば、バス停を敷地内に置いての運用も可能ということだと思うので、ぜひそのように羽後交通に打診してほしい。 |
警察庁「信号機設置の指針」では、隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認するおそれがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではないとされております。 バス停設置のご提案については、ご希望の運行ルートが不明なため、現時点では回答致しかねます。 詳細について別途ご連絡いただけますと幸いです。 |
| 駐車場の出入りに関する調査が二日間、各2時間のみというのは少なすぎるのでは無いか。 雨天、晴天、平日、休日、春夏秋冬、あらゆる状況での確認をしたうえで再度対策を再考、判断してほしい。 |
開所後は、センターに訪れる人の増加や国道107号から108号へ通じる市道開通により、交通状況の変化が想定されるため、今後も定期的に交通量調査を行ってまいります。 |
| 学校でも運営業者でもどちらでもいいから送迎をしてほしい。 車での送迎ではなく徒歩でも構わないので、移動中に不測の事態が発生した場合に対応できる状態を保ってほしい。 移動中の安全確保をもっと真剣に考えてほしい。 |
学校から学童クラブまでの移動は徒歩となります。 年度初めの4月から5月の間は業者による見守り・誘導を予定しております。 また、学校や運営事業者と連携して移動中のきまりごとを児童たちに周知し、安全に登所できるよう指導いたします。 |
| 児童が歩くであろう時間帯に実際に歩いてみたか? 自分の足で歩いてみないと必要な対策はわからないのでは? また、実際に同年代の児童に協力を要請して歩いて貰い、事前に対策すべき点を洗い出すなどの対策はとったのか? |
児童たちに学校から学童クラブまでのルートを歩いてもらうような検証はしておりませんが、市教育委員会が実施する通学路点検に同行して本荘東小学区内の通学路について確認しました。 危険と思われる箇所については必要な対策を施していくほか、児童への指導や保護者のみなさまへの情報発信を通じて事故防止に努めてまいります。 |
| 送迎について、今までは往復2キロ、迎えに出発して帰宅するまで五分で可能な環境であったものが、今後は往復16キロ・家を出てから帰宅まではスムーズに出入りができたとしてもおそらく30分以上を要するものになる。 これは夕刻という重要な時間帯に負荷をかけ、家庭のタイムスケジュール、ひいては児童の生活に多大な影響を及ぼす可能性が高いが理解しているのか。 児童の食事や入浴といった生活動作を行い睡眠時間を確保、いままでの生活を維持するためには仕事を制限せざるを得ない保護者がでるのではないか。 仕事の制限による失職や賃金の低下だけではなく、純粋な必要ガソリン代も跳ね上がることで金銭的負担が増大しているのだが理解しているか。 |
学校統合は、少子化が進む中においてもより良い教育環境を維持するために行うものでございますが、一方で統合後の学校の位置によっては、これまでに比べて距離的な負担等が生じてしまう方が一部にいらっしゃることは承知しており、本荘東小学校の学童クラブ設置においても同様のことと考えております。 新しい環境での生活が始まることにより、ご家庭での生活スタイルへも影響が出てしまうこととは存じますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| 夏の熱中症対策や冬の吹雪対策について具体的なものを事前に確認したいから提示してほしい。 | 下校の際は、学童クラブへの移動に限らず、暑さ指数が基準を超えるような日をはじめ、気象状況や付近における鳥獣の目撃情報等、児童の下校に支障があると考えられる場合には、教育委員会と協議のうえ児童を下校させずに学校で待機させるなどの対応をいたします。 その際、保護者の方々にお迎えをお願いする場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 また、夏場は水筒の携行、冬場は十分な防寒対策にご協力をお願いいたします。 |
| 市の都合による廃校で最寄りの学校を奪われる地域の家庭に対してあまりに不実では無いか。 距離的だけを考えればたいしたことがないのは確かだが、土地勘の有無という重要な情報を無視しないでほしい。 学校と離れた位置の学童に通う児童は「家から学校とその近隣地」を歩くのだから、遠隔地から通学している児童とは前提条件がまるで違う。 たった500mで一本道だからといって小学生の実子を子供だけの集団で上野駅から御徒町駅まで歩かせたいと思うか? 大げさとは思わず、土地勘の無い道の徒歩移動に保護者がどれだけ不安を感じているかを理解してほしい。 |
市内小学校においては、入学当初の一年生の下校時には教師による付き添いが行われており、東小学校においても同様に実施するように調整しております。 また、市といたしましては、新年度開始2カ月程度は専門の誘導員を学校から学童クラブまでの経路に配置することを予定しておりますので、児童の皆さんが慣れるまでの間は安心して通うことができると考えております。 ※期間等については状況をみながら調整いたします。 併せて、学校、学童クラブにおいては、児童たちへの交通安全についての指導を徹底してまいります。 児童たちが一日でも早く新しい環境に慣れることができるよう、ご家庭においてもご指導やお声がけをお願いいたします。 |
| 熱中症対策はどのあたりまで具体的に考えられていますか? 子供は背が低い分だけ、道路からの照り返しで輻射熱を強く受けるため、体感温度は+3度程度と考えて対策するのが一般的です。 子供の体感温度として考えた上で、WBGT値が警戒以上になった日がどれだけあるか把握していますか? 具体的な対策はかんがえられているのでしょうか、とても心配です。 |
近年の気象状況の変化とその危険性については、市ならびに教育委員会としても常に警戒しており、暑さ指数については学校でも日常的に測定しております。 気象状況だけに限らず、付近で鳥獣の目撃情報があった場合などにおいては、児童を下校させずに学校で待機させ、保護者の方々へお迎えを依頼する場合もございますのでご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 一般の施設利用者との接触事故が不安なので、ハードでもソフトでもリカバリでもいいので何かしら具体的な対策をしてほしい。具体的に言えばハードとして「入り口は別途作る」ソフトとして「児童の移動時間帯と一般利用者の利用開始・終了時間が絶対に重ならないような対策案」など。 こうして予め利用予定者が事前に警告や回避案を出しているが、それを加味せず運用開始し事故が発生した場合、運営及び行政側の責任負担割合を背負うようなリカバリの対策案がほしい。 |
市民交流学習センターのホールに仕切り壁を施工して、学童専用スペースと一般の利用部分を区分けします。 学童利用中に児童と施設利用者が接触する場面はほとんどないと考えておりますが、事故等の発生がないよう十分注意してまいります。 なお、学童専用スペースから講堂や外広場等に移動する際は、スタッフが同行して誘導いたします。 |
| 由利本荘市放課後児童健全育成事業業務委託の公募型プロポーザルの実施についての要綱を確認したが、行政センター内で学童を運営するにあたって具体的な諸注意に関する規則が見つけられなかったがどこか。 これだけ懸念事項が多いのに対策を講じていないわけではないはずだが、後日通達で業者は対応できるのか。 |
公募型プロポーザルは、参加者からの企画提案内容等を評価して事業者を選定するものです。 仕様書には、市民交流学習センター内での事業実施にあたり、児童の健全育成や、安心してお子様を預けて働くことができるよう、安全面に配慮した運営を行うこと等を記載しております。 プロポーザルの参加者が提案する運営方針、安全対策等について十分に審議したうえで、事業者の選定を行います。 プロポーザルが終了し、結果をHPで公開いたしました。 |
| 運営会社はいつ決まるのか。希望者がいなければ市の運営になるのか。 応募が一社しか来なかったら期待できない運営だったとしてもそこに決まってしまうのか。 |
運営事業者を選定する公募型プロポーザルを実施し、結果をHPに掲載しました。 |
| アプリはどのような仕様なのか。 到着を知らせるのではなく、想定した時間に到着しなかった場合に何かしらの挙動を行うものの方が望ましいのでは? また、アプリを導入させるのであれば、同アプリ内で利用予定日や今月の利用日の確認や変更、利用状況と請求金の確認程度はできるものにしておいてほしい。 |
アプリは委託先業者が導入するもので、児童の登所・降所時間の管理、出欠席の連絡、保護者アンケート、緊急時の一斉連絡等が可能な仕様を想定しています。 詳細は委託業者決定後にお知らせいたします。 |
| 不安を解消するために携帯電話を持たせるつもりですが、そのあたりの規則や運用などは小学校と連携がとれていますか? | 携帯電話については、学校と学童クラブそれぞれから示されるルールを守って利用させてください。 故障、紛失、盗難等につきましてもご自身の責任において、お子様に持たせてください。 |
| 「子育てが楽しいまち由利本荘市」「地域で子どもを育てる」「地域ぐるみの見守り体制の構築」という理念は素晴らしいと思う。 その理念を実行する機会を保持するため、現在運営中の学童保育は継続する方向と考えて良いのだろうか。 |
小学校の統合に伴い、本荘東小学校区内の学童クラブについても集約する方針としております。 |
説明会等でいただいたご意見・ご質問
| ご意見・ご質問 | 回答 |
|---|---|
| 事業者の選定について。学童クラブの運営になんのノウハウもない一般企業が入ってくる可能性もあるのか。社会福祉法人に限定しないで募集をかけるという認識で間違いないか。 |
業者の募集方法については公募型プロポーザルという形を取ります。 学童保育は、第2種社会福祉事業という位置づけになります。応募をいただいて、市が評価する際に、業者の経験や実績は高く評価される項目です。 したがって、仮に一般企業が選定されたとしても実績のある会社が運営することになると考えております。 |
|
施設前の国道107号線は夕方大変込み合う。保護者が迎えに来る際の混雑について、シミュレーションはしているのか。 |
昨年2日間にわたり夕方5時から7時まで交通量調査を行い、センターに出入りする車の量と待ち時間を確認しました。調査した結果では、渋滞は確認できませんでした。 |
|
敷地内北側に歩行者専用入り口を作るとのことだが、児童は駐車場内を歩くのか。 |
調整中ではありますが、専用入口から駐車場の端を通って玄関まで歩けるよう整備と誘導員の配置を考えております。 |
|
放課後の通所時、学校から施設まできちんと付き添ってくれるのか。またその期間は。 |
業者による誘導員の配置を検討しております。 期間は4月から5月末を予定しておりますが、冬場など状況に合わせて対策を講じてまいります。 |
|
アプリの用途について。 |
保護者の方にアプリをダウンロードしてもらい、通所のお知らせや緊急時の連絡等を想定しています。 |
|
80人から120人の利用を想定しているとのことだが、来所時のシミュレーションはしているのか。 |
学校から出発する時点で一度人数整理を行い、一定数の塊を作って歩いていただく形をとりたいと考えています。学年により下校時間が変わることへも対応します。 |
|
施設内で一般の方との接触を避けるとすれば、活動も制限されてくると思う。子どもたちのことも考えた活動内容、運営を考えてほしい。 |
職員の見守りのもと、外の広場で遊んだり、予約がない時には講堂を使って遊ぶことも取り入れてまいります。 |
|
外の広場に10台分の駐車場を作る計画のようだが利用者への影響は。 |
駐車場周辺に簡易的なネットや柵などの設置を考えています。 学童は日曜・祝祭日は休みなので、利用者もこちらの駐車ペースを使用してもよいと考えています。 |
|
児童たちの声が建物内外に響くと予想されるが、利用者からのクレームにならないかということも心配である。 |
施設内の防音対策を講じてまいります。 |
|
広場への遊具等の設置は検討しているか。 |
一般の方の利用もあるため、固定物設置の検討はしておりません。 |
|
現状の改修案だと、どのように改修されるのかイメージがわかない。 |
今後、改修図面をお示しできるよう準備してまいります。 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども家庭センター
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-24-6318 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。