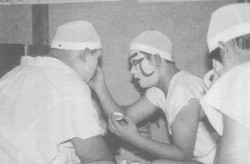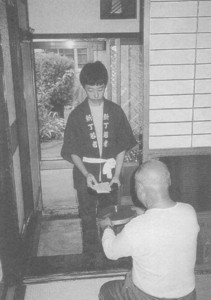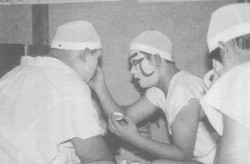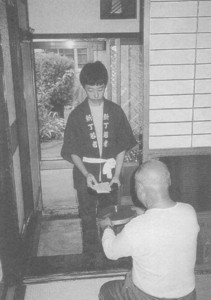| また、花配りの係は遠い部落の方に花配りに出かける。祭典の各係分担は丁内によっていくらか違いはあるが、総指揮者・副指揮者(共に腕章と笛)・連絡係(腕章)・会計係・配り物係・練り子係・笛・太鼓・三味線・人形・山車の梶棒・警護・仮装・音楽係・賄い係などである。全員準備が出来たところで出陣式の行事を行い、集合時間に合せて出発場所の大川原に集合する。 |
| 大当番七日町若者衆は、仮装と子ども太鼓は午前6時に集合し着付けや化粧をする。 |
| 午前7時50分に出陣式を行い、仮装の回らない丁内にご披露のため8時観音堂を出発、菊地跡地→山寺→下山寺→東中央線→棚木田→栄町→栄町北線→エッソスタンド曲渕→栄町町会館→大川原へ、山車集合時間に間に合わせる。 |
| 午前9時半、大川原山科整備工場附近に集合した六丁の山車は、七日町の山車の前に連絡員が集合し、安全対策を中心に注意事項を確認し、山車出発時刻9時45分、総指揮の七日町若者頭柴田聖二氏の笛の合図で、小雨の中六丁一斉に打ち鳴すお難子に共に水上・新丁・舘町・城新・田中町・七日町の順に山車が出発した。 |
| 山車に乗る係は、子ども大太鼓1人、小太鼓2〜3人、若者衆笛2〜3人、三味線1人(最近は高校生が主)、若者衆人形係1人、後方幕の中に会計係2〜3人。山車の梶棒係2〜3人、練り子係、綱引き係、車押し係、山車警護係などである。 |
| 山車のお囃子し、三味線と笛に合せ子ども等の打つ太鼓で、「祇園ばやし」「剣ばやし」「さいさいばやし」(町内により「さいさいぶし」と呼んでいる所もある)などである。山車からのお囃子がやみ、山車が止まると、音楽が鳴り出し仮装の踊りが披露される。終るとまたお囃子が始まり、山車が動き出す。その繰り返しで町内を回る。 |
| 14年の各町若者衆の山車の出し物と仮装踊りは次のとおりであった。 |